
マリー・アントワネット王妃といえば、今では多くの映画、演劇、小説で「悲劇の王妃」として有名。
ここでは、多くは語らず、ただ、革命当時、出身がオーストリア皇室だったことから「オーストリア
の淫売女」「オーストリアの牝狼」と野次られ、王政崩壊後、ギロチン(余談1)で断頭されて果てた
フランス王妃、とだけ述べておこう。
大革命200周年の1989年、パリマッチ誌が行なったアンケート調査によれば、200年前に御先祖
たちが熱狂しながら喜んだ王妃の処刑について、「不当」「許せない」と半数近くの人々が批判的
な見方をしている。
そして、200年目の王妃の命日には、当時の革命広場(現コンコルド広場)には、約一万人の
人々が集まり、ギロチン台が設置されていた場所に、白いゆりの花(王家の紋章)を捧げ、その
参列者の中には、駐仏アメリカ大使も加わっていたという。
人々が集まり、ギロチン台が設置されていた場所に、白いゆりの花(王家の紋章)を捧げ、その
参列者の中には、駐仏アメリカ大使も加わっていたという。

また本物の弁護士を使って、もう一度、国王裁判をやり直した番組、フランスTF1制作の「ルイ
16世再審裁判」では、視聴者の投票により判決を下す形式であったが、結果は、追放17.5%、
死刑27.5%、そして無罪が55%となって、当時の大法廷裁判所の衣装をまとった裁判長が
「判決は無罪。これにて閉廷」と高らかに宣告。法廷は満場の拍手につつまれた。
これらフランス国民がそっくり200年前にタイムスリップしていたら、マリー・アントワネット王妃
もギロチンで処刑されることもなかったろうに・・・・などと他愛のない妄想もいだいてしまう。
Louis XVI 

しかし、国王ルイ16世処刑についてインタヴューされた当時のベレゴボワ首相が、政治的死刑
には反対の意見を表明してから、冷静にこう言った。「しかし、1793年の時点で、私は同じことを
考えたかどうかは分からない」と。

つまり、上記のアンケートや裁判は、はっきり言って「茶番」なのである。ただ時代の変遷を
物語るだけの試みに過ぎない。当時、少なくとも、革命は肯定され、王家は否定され、民衆は
熱狂していた。革命に積極的な参加態度を示さぬ者は、それだけで反革命容疑をかけられて
投獄、いとも簡単に処刑されたりしていた。
民心は操作され、思想は統制され、傍観者は危険分子と目され、皆が皆、熱烈なる革命党員
でなければ、その生命も保証されなかったという極度な緊張状態にあったのだ。誰が、国王
や王妃の処刑に反対などするだろうか? 狂喜乱舞して処刑に喝采を送ったに違いないのだ。
や王妃の処刑に反対などするだろうか? 狂喜乱舞して処刑に喝采を送ったに違いないのだ。

ところで、そんな恐怖政治(テルール)の下、つまり、少しでも革命に消極的であったり、無関心
であったりしただけで「容疑者」扱いされ、密告ひとつでギロチン送りになるような狂気のパリで、
こともあろうに、この王妃を救い出し、外国へ逃がそうと黙々と活動していた者たちがいたのだ。
国民一人一人がすべて監視人だったような暗黒のパリで、これら大胆不敵、奇想天外、恐れを
知らぬ無謀な計画は、着々と準備され、実行に移されていたのである。

しかも、ひとつやふたつではない、様々な立場の連中が、それぞれに暗躍しているのだ!
当時のパリの現実を思うと、それは、とても信じられない命知らずな無茶なのである。それを
当時のパリの現実を思うと、それは、とても信じられない命知らずな無茶なのである。それを
前提に以下の「マリー・アントワネット救出作戦」の数々を読んで頂きたい。
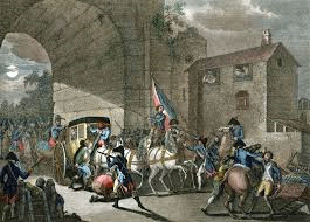
まず、これは有名なヴァレンヌ逃亡事件。
すでに、過激な民衆が王宮に乱入して近衛兵を虐殺し、王室の人々に危害を加えようなどと
いう事件も起こり、革命が凶暴化しつつある頃、フェルゼン伯爵が首謀者となって、王室を危険な
いう事件も起こり、革命が凶暴化しつつある頃、フェルゼン伯爵が首謀者となって、王室を危険な
パリ(王室はヴェルサイユ宮からパリのチュイルリー宮へ強制移送されていた)から脱出させよう
という計画が立てられた。
このフェルゼン伯爵、スウェーデン王国の貴族であるが、パリに遊学の最中のある夜、オペラ座
の仮面舞踏会でお忍びで参加していたマリー・アントワネット王妃と意気投合、彼女もすっかり
この外国の貴公子に魅了されてしまい、ついつい仮面をとって身分をあかしてしまう。その夜の
出会いから、この一編の恋物語は始まった。
当時の駐仏スウェーデン大使クルツも本国の国王への密書に、マリー・アントワネット王妃が
フェルゼン伯爵に特別な想いを抱いているようである、と報告していることからも分かるように、
フェルゼン伯爵に特別な想いを抱いているようである、と報告していることからも分かるように、
オペラ座のロマンティックな夜から二人の仲は秘めるに秘められぬ「本物」になっていたようだ。

フェルゼンはスウェーデン王国軽騎兵中佐であったが、何かにつけて王妃が喜ぶことを望んで
いた、底なしのお人好しルイ16世は、彼を駐仏スウェーデン近衛隊大佐に任命して、フランス
滞在を許可した・・・・。
フランス革命勃発は、このフェルゼンにとって、恋人の身に迫った危険以外のなにものでもない。
この甘いマスクの美貌の騎士は、フランス王妃の愛人になって甘い汁を吸おうなどというケチな
色男ではなかった。
王妃の周辺に群がっていた「親しいお仲間たち」は、とっくに彼女を見捨てて外国へ亡命して
いる。彼一人が、革命のパリに踏みとどまって、王妃の身を案じているのだ。
いる。彼一人が、革命のパリに踏みとどまって、王妃の身を案じているのだ。

だから彼は、インディー・ジョーンズさながら、超人的な動きを見せる。ロマンティックな活劇小説
そのものを地で行くような行動に出る。
友人の名を使って偽造旅券の手配をし、資金を集め、国境付近の軍隊と連絡し、大型馬車
から一本のシャンパンに至るまでの物資の調達にと、東奔西走した。当時の王室は、衆人環視
から一本のシャンパンに至るまでの物資の調達にと、東奔西走した。当時の王室は、衆人環視
そのものの状況であり、無論のこと、衛兵は随所に立っているし、従僕やら召使やら侍女やら、
色々な係員やらの大群がびっしりと周囲に雑居していた。王族の人々が夜闇にまぎれてとは言え、
宮殿を抜け出すなんて芸当は、まさしく至難であった。

しかし、歩哨が背を向けた瞬間に後ろを横切り、衣装ダンスに隠された秘密の出口を抜け、
馬車の物陰に隠れて進み、また衛兵のたむろする部屋を何くわぬ顔で通過したり、まったくの
馬車の物陰に隠れて進み、また衛兵のたむろする部屋を何くわぬ顔で通過したり、まったくの
綱渡りの曲芸じみたこの宮殿脱出作戦は、まんまと成功するのである。
そして従僕に変装した国王ルイ16世、侍女姿のマリー・アントワネット王妃、女装の王太子
に内親王ら王室の人々は、日雇い御者の扮装のフェルゼン伯爵の馬車に乗り込んで、闇夜の
街道を疾走したのである......
に内親王ら王室の人々は、日雇い御者の扮装のフェルゼン伯爵の馬車に乗り込んで、闇夜の
街道を疾走したのである......

翌朝、国王一家の逃亡を知らされた王宮警備責任者のグーヴィヨン将軍は、取り乱して「魔法
か手品によるほか不可能だったはずだ!」と絶叫したとのこと。
フェルゼン伯はボンディーで一行と別れる。そして王室一家を乗せた馬車は3人の特命を帯び
た近衛兵に守られながら東へと向かう。
道中、何事もなく、広がる田舎景色に一行の心も和み、ちょっとしたスリルを含んだピクニック
とでもいった感覚が強くなってくる。
パリは国境に近い都だ。敵が国境を突破するとすぐに首都は危険にさらされたものだ。しかし
今回は、それが幸いしていた。もう、国境は近い。
Jean-Baptiste Drouetとアッシニア紙幣 



ところが、サント・ムヌーという町の駅長ドルーエが、代金として支払われた紙幣に印刷してある
国王の肖像画と車中の人物が酷似していることに気づいてしまう。

これは後世に作られた挿話らしいが、ともかく、この男は、馬車が町を出て2時間ほどした後に、
王室一家のパリ脱出の報を携えた早馬を迎えて、あわてて馬車を追跡した。

彼はヴェルダンへ向かうつもりであったが、馬車はこのときヴァレンヌへ向かっている。この
段階では運はまだ王室にあった。
段階では運はまだ王室にあった。
しかしクレルモンという村で、彼は旅支度の大型馬車が御者に「ヴァレンヌへ行け」と声を掛けて
いるのを小耳にはさんだ男と会ってしまう。
この名もない男の証言によって、ドルーエはヴァレンヌへと方向転換。そして、ついに、ヴァレンヌ
の小村で馬車に追いついたのだ。
旅の馬車の中に国王一家が乗っているという騒ぎで、たちまちこの村に近隣の住人らが押し
かけてくる。「パリへ戻れ! さもないと銃撃するぞ」の声がわき起こった。
かけてくる。「パリへ戻れ! さもないと銃撃するぞ」の声がわき起こった。

もはや、完全に脱出は失敗である。

王室一家はその夜は村の助役ソースの家の粗末な寝台に眠ることになる。興奮した群集の
中には家の中にズカズカと入ってきて、王家の人々を見物していくような無礼者もいた。ただ一
人、ソース氏の祖母だけが、無邪気に眠っている王子らの手に接吻し、彼らの不運に落涙して
いたという。大御代(ルイ14世の時代)の生まれだったこの老婆にしてみれば、王家の人々に
対する村人らのあまりの非礼に、命も縮まる思いだったのだろう。
中には家の中にズカズカと入ってきて、王家の人々を見物していくような無礼者もいた。ただ一
人、ソース氏の祖母だけが、無邪気に眠っている王子らの手に接吻し、彼らの不運に落涙して
いたという。大御代(ルイ14世の時代)の生まれだったこの老婆にしてみれば、王家の人々に
対する村人らのあまりの非礼に、命も縮まる思いだったのだろう。
ともかく一行は、群集の罵声の中、パリへ送還されることになる。
実は、ここに、もう一つの不思議があった。

王室一家の馬車は、群集に取り巻かれて街道を引き戻されて行ったわけだが、騎馬の者は
200そこそこで、他は女子供も混じる烏合の衆。そこに、国境から王室一家を保護すべく駆け
つけたロワイヤル・アルマン連隊が接近してきたのである。指揮官はブイエ侯爵である。七年
戦争、アメリカ独立戦争にも派遣されたこの将軍が、なぜか、この烏合の衆に攻撃をしかけな
いで、エール川という小さな川の向こうで撤退してしまったのだ。
200そこそこで、他は女子供も混じる烏合の衆。そこに、国境から王室一家を保護すべく駆け
つけたロワイヤル・アルマン連隊が接近してきたのである。指揮官はブイエ侯爵である。七年
戦争、アメリカ独立戦争にも派遣されたこの将軍が、なぜか、この烏合の衆に攻撃をしかけな
いで、エール川という小さな川の向こうで撤退してしまったのだ。
マリー・アントワネットにつきまとう不思議な現象のひとつである。

なんであれ、こうして、一幕の冒険譚は終わりを告げた。
しかし、この事件以来、王室一家は本物の囚人と化し、立憲君主制度などという温和な政治
形態は崩壊、革命は過激化していったのだ。
形態は崩壊、革命は過激化していったのだ。

 ランバル大公妃の虐殺
ランバル大公妃の虐殺 王妃のお気に入りで最後まで忠節をつくしたランバル大公妃など監獄で乱入した民衆に虐殺
されている。もはやパリは地獄絵図の様相。(余談2)
されている。もはやパリは地獄絵図の様相。(余談2)
ここに、フランソワ・アドリアン・トゥーランFrancois Adrien Toulan (1761-1794)という男がい
る。革命以前は楽譜商をしていた三十男である。王宮に民衆が殺到し、近衛スイス部隊を虐
殺した八月十日事件の参加者というくらいだから、熱烈な革命党員である。
る。革命以前は楽譜商をしていた三十男である。王宮に民衆が殺到し、近衛スイス部隊を虐
殺した八月十日事件の参加者というくらいだから、熱烈な革命党員である。
今では亡命者財産管理局長、ついでコミューン委員を務める革命政府の要人である。
ところが、同志トゥーラン(革命家同士はこう呼び合った)、どうしたわけか、国王一家の監視
の任についている内に、すっかり熱烈な王党派に豹変してしまう。
の任についている内に、すっかり熱烈な王党派に豹変してしまう。


.............................................Marie Antoinette............................90年代に描かれたダヴィッドのデッサン画
マリー・アントワネット王妃がよほど魅惑的だったのか、はたまた魔女めいた妖力でも秘めて
いたのか、バリバリの革命党員が、一命を投げ打って王妃への奉仕に順じたり、突然として深
い同情を示すようになったり、やけに好意的な態度をとるようになったり、そんなケースがやた
らに多いのだ。これには驚かされる。
いたのか、バリバリの革命党員が、一命を投げ打って王妃への奉仕に順じたり、突然として深
い同情を示すようになったり、やけに好意的な態度をとるようになったり、そんなケースがやた
らに多いのだ。これには驚かされる。
既述したが、この時期は極端に緊張しており、些細な言動挙動ひとつで、文字通り命取りに
なるような恐怖政治下にあった。それを思うと、どう考えても、マリー・アントワネット王妃に関し
ては、人を魅了する尋常ではないパワーの持ち主と言わざるを得ない。
なるような恐怖政治下にあった。それを思うと、どう考えても、マリー・アントワネット王妃に関し
ては、人を魅了する尋常ではないパワーの持ち主と言わざるを得ない。

ともかくこの革命の闘士トゥーランは、処刑間近で家族から離されてしまった国王ルイ16世
の伝言を新聞の売り子を買収して王妃に伝えたり、国王が形見として王妃の元へ人を介して
渡そうとして失敗、当局に没収された指輪を、盗み出してまでして王妃の手元へ届けたり、全く
彼は命の危険などかえりみず、細々と王妃への奉仕に貢献していた。
の伝言を新聞の売り子を買収して王妃に伝えたり、国王が形見として王妃の元へ人を介して
渡そうとして失敗、当局に没収された指輪を、盗み出してまでして王妃の手元へ届けたり、全く
彼は命の危険などかえりみず、細々と王妃への奉仕に貢献していた。
そして、国王が処刑された翌日、彼はついに重大な決意を固めた。王妃が幽閉されているタ
ンプル塔から彼女を脱出させ、イギリスへ逃がそうと。
ンプル塔から彼女を脱出させ、イギリスへ逃がそうと。


Tour du Temple タンプル塔のルイ16世
王妃はこの計画をトゥーランから持ちかけられ、当然、信じられぬ思いだったろう。まさか、
革命政府の幹部からこんな計画を打ち明けられるなどとは夢にも思わぬからだ。そこで、慎重
に、パリに潜伏していた王党派のジャルジェイ将軍との連携を提案して、自分の短信を持たせて
に、パリに潜伏していた王党派のジャルジェイ将軍との連携を提案して、自分の短信を持たせて
トゥーランを将軍の元へ派遣する。(ジャルジェイ将軍は、正式にはmarechal de camp、つまり
野戦総監。1675年以降は「少将」に相当)


Francois Augustin Regnier de Jarjayes なぜか「ベルばら」ではオスカルの父(余談3)
こんどは驚いたのはジャルジェイ将軍だ。こんな過激な革命党員の訪問を受けては、いよい
よ自分も尻尾をつかまれたかと思うに決まっている。ところが、このコミューン委員の口から出
たのは王妃救出作戦の話であり、確かに王妃直筆の手紙を持参している・・・・
よ自分も尻尾をつかまれたかと思うに決まっている。ところが、このコミューン委員の口から出
たのは王妃救出作戦の話であり、確かに王妃直筆の手紙を持参している・・・・
そこで、今一人、金によって市の役人ルピートルを味方につけて、このトゥーランの作戦は実
行へと進んでいくのだ。
行へと進んでいくのだ。


.........Le prince Louis-Charles...........................Elisabeth Philippine Marie Helene de France
役人たちのタンプル塔の囚人巡回業務は大変に面倒臭がれており、代役は歓迎されていた。
そこで、トゥーランとルピートルは積極的に気の良い友人となって仲間たちの夜勤を交代して
やった。
彼らは夜警の際には、服を2枚重ね着して行き、王妃とその義妹エリザベト王女が市の役人
の服装に変装できるように手配した。王子は洗濯物運搬のカゴの中に入れて運び出す。
の服装に変装できるように手配した。王子は洗濯物運搬のカゴの中に入れて運び出す。
 夜のタンプル塔
夜のタンプル塔 ドーヴァー海峡までの馬の手配や脱出が発覚してから追っ手が出発するまでの時間的な計
算も緻密になされており、タンプル塔の牢を出てしまえればあとは楽観できた。
算も緻密になされており、タンプル塔の牢を出てしまえればあとは楽観できた。
問題は旅券の偽造だが、ルピートルは旅券関係の委員長をしていたので、「本物の偽物」が
発行できるのだ。これは極めて有利だった。
発行できるのだ。これは極めて有利だった。
しかし、この、旅券の作成にかなりの時間が消費される。
この間に予想だにしなかった障害が発生してしまった。

それは前線の司令官だったデュムーリエが敵軍と結託してパリへ攻撃をしかけてくるという事
件の勃発だった。デュムーリエが部下の抵抗にあい逃亡、この事件は未遂に終わったが、国
境に戒厳令がしかれてしまい、脱出計画の実行が極めて危険視されたのである。
件の勃発だった。デュムーリエが部下の抵抗にあい逃亡、この事件は未遂に終わったが、国
境に戒厳令がしかれてしまい、脱出計画の実行が極めて危険視されたのである。

そこで、陰謀家ジャルジェイ将軍は王妃だけの脱出計画に変更すべきと申し出る。
しかし子供たちを残してゆくことを王妃は拒絶。
計画は全面的な中止となった。
その後、トゥーランは密告によって捕らわれたが、脱出。しかし逃亡先で再逮捕されて、パリ
でギロチンに果てた・・・・
でギロチンに果てた・・・・
 Marie Therese Charlotte de France
Marie Therese Charlotte de France 不可思議な男である。やはりタンプルに幽閉されていた王妹エリザベト王女にも、自分の帽
子と国王の帽子をこっそりとすり替えて持ち出して、王女にその最愛の兄の形見として王の帽
子を手渡したという大胆不敵なほどの誠意を示している。牢内で国王の玉璽が消えた事件で
大騒ぎしている時に、国王一家で唯一生きて解放された長女マリー・テレーズ王女はその手記
に「私は犯人を知っている。王家に好意をもっているある男だ。私はこの勇敢な男の名は言え
ない」と書き込んでいるが、その男こそトゥーランだ。
子と国王の帽子をこっそりとすり替えて持ち出して、王女にその最愛の兄の形見として王の帽
子を手渡したという大胆不敵なほどの誠意を示している。牢内で国王の玉璽が消えた事件で
大騒ぎしている時に、国王一家で唯一生きて解放された長女マリー・テレーズ王女はその手記
に「私は犯人を知っている。王家に好意をもっているある男だ。私はこの勇敢な男の名は言え
ない」と書き込んでいるが、その男こそトゥーランだ。
通行証によると、彼は中肉中背、茶色の髪、165センチの身長。獅子鼻。・・・そんな男だっ
た。
た。

ここに、もう一人、あまり名の知られていない貴族が登場する。
バッツ男爵ジャンである。
南仏ベアルン地方出身の旧家の出とも言われているし、軍隊に入るための貴族称号を手に
入れただけのガスコーニュ地方の次男坊とも言われている。幸運にも相場があたったおかげ
で、かなりの資産家ではあったが、革命の起こるまでの平穏な時代にあっては、何ら表に出て
くることもなく、女優を情婦に囲って、ぐうたらの成金男らしい無為徒食の日々を送っていた。
(ダルタニャンとかのバッツ家との繋がりを主張し、バッツ・トランケレオン系の家柄を系図学者
に申請している)
入れただけのガスコーニュ地方の次男坊とも言われている。幸運にも相場があたったおかげ
で、かなりの資産家ではあったが、革命の起こるまでの平穏な時代にあっては、何ら表に出て
くることもなく、女優を情婦に囲って、ぐうたらの成金男らしい無為徒食の日々を送っていた。
(ダルタニャンとかのバッツ家との繋がりを主張し、バッツ・トランケレオン系の家柄を系図学者
に申請している)
ところが、ひとたび革命が起こるや、彼はいよいよ「人生の本番」を待っていたかのように、
楽屋裏から舞台の上に飛び出してきた。
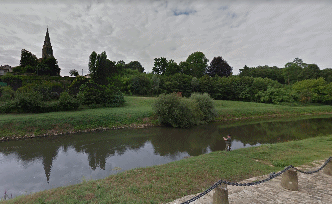

バッツ男爵の生地タルタスの田舎町 1754年1月27日の男爵の洗礼証明書
まずはルイ16世をタンプル塔の牢から救出しようと暗躍し、それが失敗すると、腹いせまぎ
れに、ルイ16世をギロチン台へと護送する荷車の前を「国王万歳!」と叫びながら横断すると
いう、なんとも無茶苦茶な奇行をやってのける。
れに、ルイ16世をギロチン台へと護送する荷車の前を「国王万歳!」と叫びながら横断すると
いう、なんとも無茶苦茶な奇行をやってのける。
自殺行為以外のなにものでもないが、どうしたわけか、このバッツ男爵、逃げおうせてしまう。
かなり不可解な人物だが、男爵は投機の成功で蓄えた全資金を革命政府の要人の買収に
費やし、その狂気じみた冒険家の才覚のすべてを王室一家の救助に充てた。
費やし、その狂気じみた冒険家の才覚のすべてを王室一家の救助に充てた。
 Jean-Baptiste Michonis
Jean-Baptiste Michonis 彼が買収した政府の高官の中にミショニー氏という人物がいた。この人物、タンプル塔の牢
獄の理事官だ。王室が幽閉されている牢屋の幹部の要職にあった。渡りに船の人材だ。
獄の理事官だ。王室が幽閉されている牢屋の幹部の要職にあった。渡りに船の人材だ。
だが、どうにも、このミショニー氏、バッツ男爵の提供する金銭が目当てで陰謀に与したとは
到底考えられない。彼は、先出のコミューン委員トゥーラン同様、自らの意志で、陰謀に「積極
的に参加」した男の一人、と思える。
到底考えられない。彼は、先出のコミューン委員トゥーラン同様、自らの意志で、陰謀に「積極
的に参加」した男の一人、と思える。

ここまで来ると、革命政府は人民主義とか王政否定の理念すら上辺のみの腐敗しきった「無
思想」な革命家の集団のように見えてしまうが、少なくとも、「反革命」や「王党派」などという危
険分子を徹底的に掃討し、ギロチンの極刑をもって、片っ端から捕縛、処刑を展開していた恐
怖政治であったことは動かせぬ事実である。
思想」な革命家の集団のように見えてしまうが、少なくとも、「反革命」や「王党派」などという危
険分子を徹底的に掃討し、ギロチンの極刑をもって、片っ端から捕縛、処刑を展開していた恐
怖政治であったことは動かせぬ事実である。
その背景をすれば、こういう大胆不敵な革命政府にとっての裏切者たちは、一体、何を考えて
いたのだろうか?
自らも、革命によって、身分や収入や名誉という恩恵に浴した者たちなのに、それらばかりか、
命までも捨てるような一か八かの計画に身を投じているのだから......
ともかく、このバッツ男爵・ミショニーのペアでまた、とんでもない救出作戦が敢行される。


男爵はすでに「フォルゲ」という偽名で国民軍兵士に登録されている。そしてタンプルの牢獄
警備隊員の任に就いていた。そしてミショニー氏は、牢獄の理事官でもあるので、難なく王妃ら
に国民軍の軍服を手渡していた。
警備隊員の任に就いていた。そしてミショニー氏は、牢獄の理事官でもあるので、難なく王妃ら
に国民軍の軍服を手渡していた。
男爵は買収しまくって何人かの男らを警備隊に加えた。
そして計画は、当日、国民軍の服をまとった王妃らを牢獄の警備隊に紛れ込ませ、王子は
一隊の内側に包み込んで、堂々と牢獄から脱出するという奇想天外なものだった。
一隊の内側に包み込んで、堂々と牢獄から脱出するという奇想天外なものだった。
ところがこの計画、見事に進行し、「世界史上、最も唖然たる、全く本当とはどうしても信ぜら
れぬ場面のひとつが出現する」(ツヴァイク)。
れぬ場面のひとつが出現する」(ツヴァイク)。
もはや、これは、映画や小説に出てくるような冒険譚である。しかも、絵空事として計画され
た空論ではなく、準備され、実行され、成功するはずの「冒険活劇」だったのだ!
た空論ではなく、準備され、実行され、成功するはずの「冒険活劇」だったのだ!

ところが、ここで、我々人間の知恵や努力を嘲笑う運命の女神の、まったく抗し難い作用が、
出来事の流れを逆転させるのである。
出来事の流れを逆転させるのである。
その夜、牢番の男のもとに謎の紙片が届けられた。そこにはこう書かれていた。「今夜ミショニー
理事官が諸君を裏切るぞ」
牢番の男は疑いも入れずに大騒ぎを始める。
そして、もしもそれさえなかったら、このフランス史上最も魅力溢れるドラマとなったであろう王
妃救出劇は、「未遂に終わった数々の陰謀」のひとつに加えられてしまったのだ・・・・
妃救出劇は、「未遂に終わった数々の陰謀」のひとつに加えられてしまったのだ・・・・
バッツ男爵ら一味は夜闇の中に姿をくらまし、翌日事情聴取されたミショニー理事官は「牢番
のバカが誰かに一杯くわされたのさ」と笑い飛ばして、この作戦は、歴史から抹殺された。
のバカが誰かに一杯くわされたのさ」と笑い飛ばして、この作戦は、歴史から抹殺された。

それにしても、先のヴァレンヌへの逃亡事件の際、追っ手のドルーエの行く先をヴェルダンから
ヴァレンヌへと方向転換させた謎の証言といい、この事件で牢番の手元へ届けられた謎の紙片
といい、マリー・アントワネット王妃の救出作戦には、何かミステリアスな作用が働いて頓挫する
ことが多い。


信じられないような行動に出る男たちも不可思議だが、また、それらを挫く謎の偶発事の発生
もまた奇怪ではある。それが、「運命」というものなのだろうか?

後述談だが、このバッツ男爵はその後も逮捕されることなく逃げおうせ、王政復古後、元帥
の位を授かった。
の位を授かった。
王妃の身柄を救うために動いていたのは、なにも潜伏する王党派だけではなく、外国の軍隊
も、自国の平安のために革命政府を叩き潰し、王妃や王子を救出しようと軍事行動をとって
も、自国の平安のために革命政府を叩き潰し、王妃や王子を救出しようと軍事行動をとって
いた。かのフェルゼン伯爵も自国スウェーデンのグスタフ国王を動かして対仏同盟軍の首脳ら
との連携をとっていた。恋の騎士フェルゼンは、国際舞台で、今度は王妃救出作戦を再開して
いたのだ。
プロイセン・オーストリア同盟軍の司令官ブラウンシュヴァイク公爵はコブレンツにおいて有名
な宣言(マニフェスト)をフランス人民に発した。「フランス国王、王妃に対して侮辱的な言動があり、
いささかでも暴力行為がなされた場合、パリを軍事制裁により焦土と化す」と。
 プロイセン軽騎兵
プロイセン軽騎兵 
しかしこの宣言は逆効果となり、外国の圧力に奮起したパリでは、宣言に応ずるようにルイ16世
の首を落として徹底抗戦の意思表示とした。

残るは王妃の命と王子の命であるが、パリへの要衝となっていたヴァランシエンヌがヨーク公
率いるイギリス・ハノーヴァー連合軍により陥落せしめられると、革命政府は浮き足立った。
率いるイギリス・ハノーヴァー連合軍により陥落せしめられると、革命政府は浮き足立った。

王妃救出に超人的な情熱を注ぐフェルゼン伯は、この機に乗じてパリへ総攻撃をかけて、
王妃の命と引き換えに有利な講和条約を申し出る計画を同盟軍に提案する。

これは的を射た提案だった。なぜなら、ヴァランシエンヌの敗北で危機感の高まっていた革命
政府側は、王妃の命という切り札を利用して、有利な講和を締結するという腹づもりでいたので
ある。フェルゼン案が採択されれば、革命政府はその条件をのむつもりだったのだ。
ところが(またしてもこの接続詞だ!)革命政府が王妃の処刑が切迫していることを同盟軍側
に信じ込ませて、その命と引き換えの講和条約の申し出を促そうと画策すると、なんと、今度は
に信じ込ませて、その命と引き換えの講和条約の申し出を促そうと画策すると、なんと、今度は
同盟軍側が二の足を踏む。
つまり、先のブラウンシュヴァイクのマニフェストによって国王ルイ16世の処刑を早まらせて
しまったあの失敗体験から、これは下手に相手を刺激すると二の舞いの結果になると慎重策
をとったのだ。つまり、フェルゼンの提案を退けて、攻撃の延期を決定した。
しまったあの失敗体験から、これは下手に相手を刺激すると二の舞いの結果になると慎重策
をとったのだ。つまり、フェルゼンの提案を退けて、攻撃の延期を決定した。




フェルゼンは茫然とした。そして妹のソフィーに「もう僕は死んだも同然だ」と手紙を書いている.....
ともかく、こうして、陰謀によらず、列強を巻き込んでの大規模な軍事行動によって王妃を救出
するというフェルゼンの二度目の計画も、ついに頓挫したのである。これもまた、フランス側の
思惑を考慮すると、かなり成功率の高い救出計画だったはずなのだが・・・・
そうするうちに革命政府は戦局の挽回を図り、王妃を本当に処刑裁判の場に引きずり出す
のであった。
のであった。

こうして、王妃マリー・アントワネットは、「ギロチンの控え間」と呼ばれていたコンシェルジュリー
牢獄へと移送される。
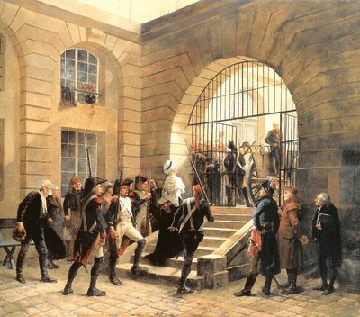
そのコンシェルジュリー牢への護送任務には、4人の警察理事官がついていた。タンプルの
庭園への潜り戸で頭をぶつけてしまった王妃に、「痛くはありませんでしたか?」と優しく声を
庭園への潜り戸で頭をぶつけてしまった王妃に、「痛くはありませんでしたか?」と優しく声を
かける一人の理事官がいた。
あのバッツ男爵と共謀して王妃を救出しようとしたミショニー氏である。
ここまで事態が切迫してしまった段階で、再び、一人の人物が登場する。
ルージュヴィル士爵アレクサンドルである。そして、この男を引き会わせたのは、先のミショニー
理事官だった。こともあろうに、氏の正式な肩書は「監獄部門を掌握せる警察理事官」である。
そんな権力者が、今ではそこいらの王党派顔負けの熱烈な「王妃の味方」なのだ!

ルージュヴィル士爵は、暴徒が王宮に乱入したおり、王家の人々を守ろうと馳せ参じた勤王
派貴族「懐剣騎士団」の一員、つまり札付きの王党員であり、情婦の密告で一度投獄されたこと
派貴族「懐剣騎士団」の一員、つまり札付きの王党員であり、情婦の密告で一度投獄されたこと
もある。「懐剣騎士団」だった貴族という告発状は、そのままギロチン決定を意味する。ところが、
警察理事官のミショニーが暗躍してこの危険人物を無罪放免にしてしまった。
彼は確かにラ・ファイエットのもとアメリカで騎兵中尉をしていた軍人だが、父親はルージュヴィル
領主とは言え、身分は徴税請負人、母親はアラスのブルジョワのユレ家の娘、先祖に遡っても
とても「帯剣貴族」とは言えない。妹たちの一人が歩兵将校に嫁いでいるくらいだ。
ただ、バッツ男爵の怪しげな身分といい、ルージュヴィルといい、大活躍する真の王党派は
生粋の名家名門の御曹司ではなく、成り上がって来た海千山千が光っている。
生粋の名家名門の御曹司ではなく、成り上がって来た海千山千が光っている。
そして恐怖政治下のパリに潜伏するこの大胆不敵な男、ルージュヴィルと、これもまた不可解
なほどに大胆不敵な革命家ミショニーが、ペアを組んで、王妃の救出作戦を開始するのである。

そして、ある日、コンシェルジュリーの地下牢の王妃のもとに、ルージュヴィル士爵が忽然と
現われた。番兵が控えているので会話も出来ない。そこで士爵は、素早く上着の裏に差してい
たカーネーションを床に投げ落とす。王妃は、かつて王宮での恐怖の夜、命がけで自分たちを
守ろうとしてくれた貴族の一人であることを見て取り、思わず目に涙を浮かべてしまった。それ
もそうだ。こんな絶体絶命の地下牢に、突然、勤王の騎士だった男が現われたのだから。
現われた。番兵が控えているので会話も出来ない。そこで士爵は、素早く上着の裏に差してい
たカーネーションを床に投げ落とす。王妃は、かつて王宮での恐怖の夜、命がけで自分たちを
守ろうとしてくれた貴族の一人であることを見て取り、思わず目に涙を浮かべてしまった。それ
もそうだ。こんな絶体絶命の地下牢に、突然、勤王の騎士だった男が現われたのだから。
感激のあまりカーネーションに気づかぬ王妃に、仕方なく士爵は小声で「カーネーションを拾って
下さい」とだけささやくと牢を出ていった。

牢獄には、多くの物見高い見学者が王妃を見に出入りしていた。ちょっとした管理官の副収入
ってわけだ。番兵からすれば、この男も、そんな連中の一人に過ぎなかったろう。
しかしカーネーションの中には、脱走計画の短信が潜んでいたのだ・・・・。
そしてその日から救出計画は着々と進行していくことになる。
当日の夜11時頃、ミショニー理事官と変装したルージュヴィル士爵がコンシェルジュリー監
獄に現われた。市当局の命令により、これから囚人(王妃)をタンプル牢に移送すると告げる。
相手は本物の警察理事官だ。コンシェルジュリー側も疑うわけもない。
獄に現われた。市当局の命令により、これから囚人(王妃)をタンプル牢に移送すると告げる。
相手は本物の警察理事官だ。コンシェルジュリー側も疑うわけもない。
しかし中庭に待機している護送馬車は、そのまま王妃を共謀者ジャルジェイ夫人のもとへ、
そして手配されたルートでドイツへと逃亡される計画だ。
そして手配されたルートでドイツへと逃亡される計画だ。
王妃を「連行」した陰謀家たちは首尾よく最後の、通りに面した門までたどり着く。その向こう側
には自由があるのだ。
 獄中の王妃
獄中の王妃 
ここでまた、「ところが」である。すでに買収されていたはずの門番が、どうしたわけか土壇場
で裏切ったのだ。「ここは通しません。部屋に戻って下さい!」と門番は叫んだ.....。
で裏切ったのだ。「ここは通しません。部屋に戻って下さい!」と門番は叫んだ.....。
ルージュヴィルは仲間に計画の失敗を告げると、何事もなかったように夜闇の中に消えてゆく。
一方、ミショニー氏は何か妙な自信でもあったのか、なぜかそのまま居残り、そして下手な弁論も
空しく逮捕、今度はついに年貢の納めどき、ギロチン台に上った....。

ここでもまた、最後の最後で不可思議な現象が起きている。門番の土壇場での裏切りである。
ヴァレンヌ事件の際の、謎の証言と、バッツ男爵計画の際の、謎の紙片。そして、このルージュ
ヴィル計画における門番の突然の離反。彼は、本物の警察理事官の命令に従って門を開けれ
ばそれで良かったわけだ。それなのに.......。
その後、逃げずに居残ったミショニー理事官の行動も解せないが、もっと解せないのが闇夜
に消えたルージュヴィル士爵の行動である。
に消えたルージュヴィル士爵の行動である。
彼は、あの作戦失敗後、腹いせに処刑場行きの国王の護送車の前を「国王陛下万歳!」と
叫びながら横断したバッツ男爵顔負けの奇行に出た。
叫びながら横断したバッツ男爵顔負けの奇行に出た。
この首に賞金のかかった男は、とりあえず身を潜めた漆喰採取場で黙々とペンを走らせていた。
題して「獄内におられる王妃にカーネーションを献上せる本人の筆になる、パリ市民が彼らの
王妃に対してなせる犯罪の数々」というパンフレットだった。彼はそれを書き終えると、国民公会
の事務局と裁判所の事務所に白昼堂々、自ら届けに行く。もはや、狂気の沙汰である。


Alexandre-Dominique-Francois Gonsse, chevalier de Rougeville デュマ「赤い館の騎士」
それでも、バッツ男爵同様、この人物、革命期を生き延びている。しかし、どうやら陰謀好き
が祟ったのか、ナポレオンのモスクワ遠征の際に、ロシア士官と通じていたとの嫌疑で逮捕、
処刑されて果てた。だが、アレクサンドル・デュマの小説「赤い館の騎士」の主人公として世に
長く名は残した・・・・。
が祟ったのか、ナポレオンのモスクワ遠征の際に、ロシア士官と通じていたとの嫌疑で逮捕、
処刑されて果てた。だが、アレクサンドル・デュマの小説「赤い館の騎士」の主人公として世に
長く名は残した・・・・。

かくして、マリー・アントワネット救出作戦のことごとくは失敗に終わり、1793年10月16日、王妃は
レヴォリュシヨン広場(革命広場。現在のコンコルド広場)に設置されたギロチン台へと護送されて
いく。(余談5)
 神父に最後の秘跡を受ける王妃
神父に最後の秘跡を受ける王妃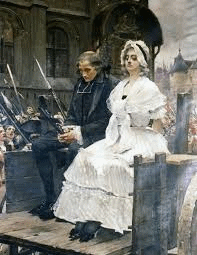
万策は尽きたはずだった。明らかに。
ところが、ここに、本当に最後の、マリー・アントワネット救出作戦が敢行されんとしていた
のである。
せむしのレース女工カトリーヌ・ユルゴンが彼女を取り巻く靴磨きや鬘師らに何やら叫んでいる。
これらパリの最下層の連中は革命期、最も過激な革命家集団を形成しており、国王に罵声を
浴びせ、貴族や近衛兵の首を切り落とし乱舞していた恐ろしく凶暴な階層である。どうせ「この
オーストリアの雌狐め!」とか「淫売女をギロチンに!」とか叫んでいるのだろう....と思いきや、彼女
が野卑な下町言葉で仲間に呼びかけている内容は、とんでもないものではないか。
こう言っているのだ。
「お気の毒な王妃を救い出すには、一瞬だって無駄にしてはいられないよ。味方を呼び集めて、
引き立てられて行く途中で囚人をさらうように、何がなんでも命令を下さなくちゃいけないよ!」
このレース女工ユルゴンに率いられた一団は、まさにパリの下層民たちの集まりで、すでに
1500名の地下組織が形成されていたのだ。
1500名の地下組織が形成されていたのだ。
本当は彼女らはコンシェルジュリー監獄に夜襲をかける手筈であった。昼間の内に界隈の街路
灯のランプに火を点し、夜間に油がきれて真っ暗になったところで、大挙して監獄を襲撃、王妃の
身を救い出すという計画だった。

これでは、かつて下層民が王宮を襲撃し、王妃らの命を狙ったのとまったく逆ではないか。彼女
たちは今度は、命がけで王妃の命を救おうと計画していたのだ。
しかし警察当局は密偵を組織に紛れ込ませ、策を弄して作戦決行を延期させ、仕舞いには
処刑当日まで、つまり手遅れの日まで引き伸ばすことに成功していた。
処刑当日まで、つまり手遅れの日まで引き伸ばすことに成功していた。
だが「フル二エのかみさん」と呼ばれていたカトリーヌ・ユルゴンは事ここに至っても王妃の身柄
を奪取する目的を放棄しなかった。かつて王宮に侍女として王妃の側近くに仕えていた女たち
までが「オーストリア女に死刑を!」と絶叫しているというのに、ユルゴンたちは黙々と作戦行動
を開始した。

もしもここで、1500人の武装集団が命がけの襲撃を王妃護送車にしかけたら?・・・・
そして、ここに、また、最後の「ところが」が割り込む。
警察は組織壊滅に密偵を暗躍させており、それが奏功したのか、現場に集合した組織メンバー
は80名そこそこだった。すでに骨抜きにされていたわけだ。
万事休す。

彼女らの目の前を王妃の護送車が通過してゆく。
そして彼女らは次々と捕縛され引き立てられて行った......。
こうして、すべてのマリー・アントワネット救出作戦は終わった。彼女の宿命を前には、あらゆる
情熱も努力も勇気も及ばず、信じられぬ成功も信じられぬ失敗によって費え去ったのだ。

12時15分、ギロチンの刃は落ちた。

もはや、誰も、彼女を、救うことは、できない。
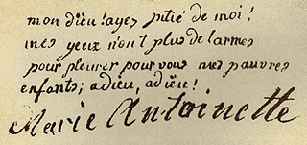
(余談1)
正確にはギヨティーヌguillotineだが、英語読みから一般的には「ギロチン」となった断頭台の呼称。
皮肉なことに、もともとは、貴族に執行されていた苦痛の少ない斬首刑の特権を、一般人にも適用
させて、従来の絞首刑とか車裂き刑とか残酷な処刑法を取りやめ、万人「平等」の苦痛の少ない
処刑法を確立するための「ギロチン」だった。
斬首は処刑人の剣によるもので、失敗すると苦痛が大きいとの執行人サンソンの意見もあり、
13世紀から存在していた断頭台を軍事外科医アントワーヌ・ルイが工夫・改善し、「ギロチン」が
出来上がる。
当初はルイ医師の名から「ルイゾン」とか「ルイゼット」と呼ばれたが、議会にこの断頭器具を
推奨することに熱心だった解剖学者ジョゼフ・イニャス・ギヨタンJoseph Ignace Guillotin博士の
名が有名となり、「ギヨティーヌ」となってしまった。
推奨することに熱心だった解剖学者ジョゼフ・イニャス・ギヨタンJoseph Ignace Guillotin博士の
名が有名となり、「ギヨティーヌ」となってしまった。


Joseph Ignace Guillotin Antoine Louis
このギヨタン博士は、まずは処刑法の平等化、そして処刑時の苦痛の軽減という人道的な立場で
これを推奨し、公開処刑は禁止し、ゆくゆくは死刑自体をも廃止するという目的があり、その大義へ
の第一歩としての改革だったので、熱心だったわけだ。
ところが、その後、革命が急進化して見世物的な公開処刑が定番となり、そんなものに自分
の名がついてしまったことに激しく抗議。もはや手遅れと知ると、一族は改姓したそうな。
の名がついてしまったことに激しく抗議。もはや手遅れと知ると、一族は改姓したそうな。
確かにそうだろう。ギヨタン博士は死刑廃止論者だったのに、大革命の大量処刑の血塗られた
象徴のような「ギロチン」に、自分の名がつくというとんでもない事態になったのだから。
博士は1814年75歳で亡くなるまで医学アカデミー、医療福祉分野で活躍したが、もはや「ギロチン」
の産みの親としか名を知られていない。
(余談2)


マリー・アントワネット王妃がフランスに嫁入りした同年に宮廷出仕を始めた公妃で、美しく控え目
で欲のないその性格ゆえに王妃のお気に入りとなり、女官長に取り立てられた。マリー・テレーズ・
ルイーズ・ド・サヴォワ・カリニャンMarie Therese Louise de Savoie-Carignan,Princesse de Lamballe
である。サヴォワ公家出身なので、かなりの名門。夫はランバル大公ルイ・アレクサンドル・スタニス
ラス・ド・ブルボンで、ルイ14世の曾孫である。(但し、1767年結婚後1年で放蕩ゆえの性病で20歳で
没っしている)

 ..
.. これに対して、やはり王妃のお気に入りとなって、ランバル公妃から女官長の地位と「王妃
お気に入り」の座を奪ったことで有名なポリニャック伯爵夫人ヨランド・マルティーヌ・ガブリエル・
ド・ポラストロンYolande Martine Gabrielle de Polastron, comtesse de Polignacは、生家も古い貴族
ド・ポラストロンYolande Martine Gabrielle de Polastron, comtesse de Polignacは、生家も古い貴族
ではあるが傾きかけており、また嫁ぎ先のポリニャック家も、過去の陰謀事件等の加担により権勢
を失っていた家柄で、彼女はお家勃興のために意図的に王妃に接近した人物である。(公爵夫人位
は1782年)


奇しくも、2人は共に1749年9月8日生まれ。しかし、運命は光と影ほどに2人の明暗を分けている。
以上のようなわけで、人柄も正反対であり、王妃が自然に好きになったランバル大公妃に対して、
ポリニャック伯夫人は目的あっての接近だったこともあり、王妃より授かった権勢を欲しいままに
享受したあげく、1789年、大革命が始まった途端に国外に亡命している。
この時期の亡命は、第一期亡命といって、まだまだ革命が本格化・長期化するなど予想も出
来ぬ段階であり、第一期に亡命した王弟アルトワ伯も国王に懇願されての亡命で3ヶ月以内に
帰国すると公言しての亡命だった。そんな中、ポリニャック伯夫人はバスティーユ襲撃の3日後
にスイスへ逃げている素早さだ。勿論、国王夫妻からの承認はあったが、逃げ足は早い。
来ぬ段階であり、第一期に亡命した王弟アルトワ伯も国王に懇願されての亡命で3ヶ月以内に
帰国すると公言しての亡命だった。そんな中、ポリニャック伯夫人はバスティーユ襲撃の3日後
にスイスへ逃げている素早さだ。勿論、国王夫妻からの承認はあったが、逃げ足は早い。



これに対して、無私無欲のランバル大公妃は、王妃の近くに留まり、結局は革命が過激化して
投獄されるまで王妃に尽くした。すでに10年以上も前からポリニャック伯夫人に全てを奪われて
いたにも関わらず、彼女は文字通り王妃、そして王室に誠心誠意の忠節を尽くして、命の危険も
伴う反革命の活動にも身を投じた。そして投獄、裁判でも革命への忠誠を拒否。


9月虐殺(Les massacres de Septembre)のランバル大公妃
そして、1792年9月に、外国軍の進撃により恐慌に陥ったパリ市民らが、監獄内の反革命分子らを
血祭りに上げよという暴動(9月虐殺)が起きて、市内各監獄が襲撃されて、収監されていた1000人
以上の者たちが虐殺された際に、彼女も犠牲となり、「元王妃のお気に入り」だった大公妃は全裸
にされて撲殺され、その首は切って落とされて、王妃がいるタンプル塔まで運ばれたという。
ちなみに亡命したポリニャック夫人はウイーンにて翌年の93年12月に病死している。
占星術的にはこの同年月日誕生の二人の女性の明暗、どう説明するのだろうか・・・
(余談3)
このジャルジェイ将軍は、Francois Augustin Regnier de Jarjayes(1745-1822)。将軍は、あの
「ベルばら」の中でオスカルの父親の設定になっている。軍人貴族の家系なのに、女子しか
「ベルばら」の中でオスカルの父親の設定になっている。軍人貴族の家系なのに、女子しか
生まれず、オスカルを男のように育てていた・・・で、あの「ベルサイユのばら」が展開していく。
しかし、現実のこのジェルジェイ氏、不思議なことに、本当に男子の後継者に縁がないのだ。

まず、上官だったブールセ中将の姪であるマリー・アンヌ・ルイーズ・ド・ブールセ・ド・ラ・セーニュ
Marie-Anne Louise de Bourcet de la Saigne(1754-86)と1770年に結婚する。生まれたのは、
マリー・アンヌ(1774-1815)だけ。このマリー・アンヌがジャン・セラファン・ゴーティエという人に
嫁ぐが、生まれたのはアンヌ・セラフィーヌとエミリー。孫の代まで女ばかり。
最初の奥さんが亡くなり、将軍は1786年アントワネット王妃付侍女のルイーズ・マルグリット・
エミリー・アンリエット・ケペー・ド・ラ・ボルドLouise Marguerite Emilie Henriette Quetpee de La
Bordeと再婚する。そして生まれたのはアンヌ・オーギュスティーヌだけ。このアンヌ・オーギュ
スティーヌは1817年、最初の妻マリー・アンヌの兄の子供であるピエール・ジョゼフ・アルマン・
ギルベール・ド・ブールセPierre Joseph Armand Gilbert de Bourcetに嫁いだが、生まれたのは
エミリー・アンリエット・ケペー・ド・ラ・ボルドLouise Marguerite Emilie Henriette Quetpee de La
Bordeと再婚する。そして生まれたのはアンヌ・オーギュスティーヌだけ。このアンヌ・オーギュ
スティーヌは1817年、最初の妻マリー・アンヌの兄の子供であるピエール・ジョゼフ・アルマン・
ギルベール・ド・ブールセPierre Joseph Armand Gilbert de Bourcetに嫁いだが、生まれたのは
マチルド。二番目の奥さんも孫まで女子のみ。マチルドは結婚したが、子はなかった。
まぁ、実は将軍はジェルジェイ家の次男、家督は長男が継いでくれているはずだと思い、将軍
の兄フランソワ・オーギュスタン(同名)の家系を見てみる。
彼はマリー・ルイーズ・ボンノMarie Louise Bonnotという女性と結婚している。そして、生まれ
たのはルイーズのみ。早くもイヤな予感だが、このルイーズは1790年マチュー・トールヌ・ド・
たのはルイーズのみ。早くもイヤな予感だが、このルイーズは1790年マチュー・トールヌ・ド・
ヴァンタヴォンMathieu Tournu de Ventavonと結婚している。そして、生まれたのがローラ・・・。
もう詳しく記すのも面倒だから、このローラも結婚相手と産んだのはルイーズのみだ。
つまり、ジェルジェイ家は、本当に、正真正銘の女系の一族だったのである !
将軍の孫娘であるアンヌ・セラフィーヌ、エミリーまで記したが、前者は結婚して3人の子をもう
けた。ジョゼフィーヌ、テレーズ、アンリエット。見事にまた娘ばかり3人。しかしだ、妹のエミリー
はエリー・ドワゼル男爵フレデリク・ヴィクトルFrederic Victor, baron Hely d'Oisselに嫁ぎ、なんと
けた。ジョゼフィーヌ、テレーズ、アンリエット。見事にまた娘ばかり3人。しかしだ、妹のエミリー
はエリー・ドワゼル男爵フレデリク・ヴィクトルFrederic Victor, baron Hely d'Oisselに嫁ぎ、なんと
ここに至ってようやくFrederic、男子誕生である。しかしこのフレデリクが亡くなるのは、もう20世紀
のこと。遅かれし、もう将軍はあの世だ。オスカル・フランソワ・ド・ジャルジェを男として教育した
将軍は正解だったのだ・・・いや、これは池田理代子氏の創作か。
 Pierre-Jean de Bourcetとその家族
Pierre-Jean de Bourcetとその家族 家系とは別の話になるが、将軍の最初の妻マリー・アンヌの兄ピエール・ジャン・ド・ブールセ
Pierre-Jean de Bourcet はルイ16世とマリー・アントワネット妃の最初の王太子だったルイ・ジ
ョゼフ(1789年6月に死去)付の首席従者で、あのヴァレンヌ逃亡の際には重要な役割を果たした
Pierre-Jean de Bourcet はルイ16世とマリー・アントワネット妃の最初の王太子だったルイ・ジ
ョゼフ(1789年6月に死去)付の首席従者で、あのヴァレンヌ逃亡の際には重要な役割を果たした
人物である。王室に忠実な一族だ。将軍の後妻の娘アンヌ・オーギュスティーヌがこの人の息子
と結婚しているのは上述の通り。


また、ジェルジェイ将軍が1786年結婚した二番目の妻ルイーズ・マルグリット・エミリー・アンリ
エット・ケペー・ド・ラ・ボルドLouise Marguerite Emilie Henriette Quetpee de La Borde
(Marguerite Louise Amelie Guelpe de la Bordeともある資料あり)、実は、将軍と結婚する時には
エット・ケペー・ド・ラ・ボルドLouise Marguerite Emilie Henriette Quetpee de La Borde
(Marguerite Louise Amelie Guelpe de la Bordeともある資料あり)、実は、将軍と結婚する時には
将軍同様に再婚だった。やはり伴侶と死別しており、彼女が王妃付侍女だった関係からか、
王妃付の音楽教師でハープ奏者だったドイツの音楽家フィリップ・ヨーゼフ・ヒンナー(1754-84)が
王妃付の音楽教師でハープ奏者だったドイツの音楽家フィリップ・ヨーゼフ・ヒンナー(1754-84)が
前夫だった。
やはりこの女性は、このヒンナーとの間にも、娘ばかり4人産んでいる。ルイーズ・アントワネット・
ロールにテレーズ・フィリピーヌにマリー・ルイーズ・ジョゼフィーヌにアントワネット・ロール・ロザリー。
もうその話は良いのだが、この四姉妹の中のルイーズ・アントワネット・ロール・ヒンナー
Louise Antoinette Laure Hinner(1777-1836)、1793年にエティエンヌ・シャルル・ガブリエル・ド・
ベル二ーEtienne Charles Gabriel de Bernyという人と結婚して、ド・ベルニー夫人となる。
Louise Antoinette Laure Hinner(1777-1836)、1793年にエティエンヌ・シャルル・ガブリエル・ド・
ベル二ーEtienne Charles Gabriel de Bernyという人と結婚して、ド・ベルニー夫人となる。
こうなると、バルザック好きの人ならばすぐにピンとくるだろう。
あの22歳年下のオノレ・ド・バルザック(1799-1850)を夢中にさせ、名作「谷間の百合」("Le
lys dans la vallee"1835)のモルソフ伯爵夫人のモデルにもなった女性である。
lys dans la vallee"1835)のモルソフ伯爵夫人のモデルにもなった女性である。


Louise Antoinette Laure Hinner Honore de Balzac
(余談4)
既存の王妃の肖像画を、パーツ毎にデジタル加工して「本物化」して、現代風の化粧を施して
リアルなマリー・アントワネットの姿を描いたり、現代のヘアスタイル、衣服と合成して現代風に
「変換」したりしている作品がネット上に色々とあって楽しい。
いわば、王妃が現代女性だったら?的な妄想.....



(余談5)
馬車馬の方へ向けて、つまり前方を向いて座った王妃に、ムシュー・ド・パリ(パリの勅任処刑
執行人の呼称)であったシャルル・アンリ・サンソンは、この絵図の通り、後方を向いて座るように
執行人の呼称)であったシャルル・アンリ・サンソンは、この絵図の通り、後方を向いて座るように
向きを変えさせた。それは、王妃が前方を見れば、彼女の首を落とすギロチン台が迫ってくる
のを見てしまうからだ。すでに9ヶ月前に国王ルイ16世のギロチン刑を執行していたこの今や
パリ中の恐怖の的である執行人サンソンは、実は心からギロチンを憎悪する優しい男だった。
パリ中の恐怖の的である執行人サンソンは、実は心からギロチンを憎悪する優しい男だった。


Charles-Henri Sanson 1989映画「フランス革命」クリストファー・リー演じるサンソン
サンソン家はすでに四代に渡りムシュー・ド・パリだった。一族は他の都市の処刑人らと姻戚
関係を結びながら、この特殊な仕事を代々担ってきていた。初代サンソンはチュレンヌ元帥旗下
関係を結びながら、この特殊な仕事を代々担ってきていた。初代サンソンはチュレンヌ元帥旗下
のラ・ボアシエール侯爵 Marquis de La Boissiereの連隊大尉だったが、たまたま出会った
ノルマンディーの処刑人一族ジュエンヌ家の娘とそうとは知らず恋に落ち、彼は軍職を捨て結婚
を選んだ(1675)。そしてパリの処刑執行人の職位を買い、サンソン家初代となった。その彼も
最初の執行の時には失神して大失敗しているくらい、この稼業は精神的負担が厳しい。
を選んだ(1675)。そしてパリの処刑執行人の職位を買い、サンソン家初代となった。その彼も
最初の執行の時には失神して大失敗しているくらい、この稼業は精神的負担が厳しい。
しかし代々サンソンの名は、各時代の大きな事件に伴って執行された様々な公開処刑が、
パリの人々に与えた衝撃と共に有名になり、憎悪や恐怖の象徴となっていく。しかしこのマリー・
パリの人々に与えた衝撃と共に有名になり、憎悪や恐怖の象徴となっていく。しかしこのマリー・
アントワネット妃の処刑に立ち会ったシャルル・アンリもそうだが、処刑される人々への憐れみと、
公開処刑にお祭り騒ぎをする群衆らを軽蔑する思いを胸に、歴代処刑人たちは黙々と職務を
全うしていたのだ。回想録にそれらの思いが克明に記されている。
またシャルル・アンリは実は根っからの王党派だった。ルイ16世処刑の日、タンプル牢からギ
ロチン台が設置された革命広場への国王の移送時、伝統的には処刑人が護送任務を行うが、
ロチン台が設置された革命広場への国王の移送時、伝統的には処刑人が護送任務を行うが、
それが、革命政府からの異例の命令で、護衛兵によって行われた。それは、国王の処刑を
妨害する王党派の暴動が懸念されたことと、彼自身がかつては国王の命令に従っていた
処刑人であり、革命への忠誠心に疑問がもたれていたからだ。確かに、それは正しかった。
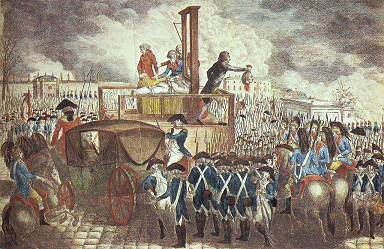 ルイ16世のギロチン刑
ルイ16世のギロチン刑 ルイ16世の落とした首を群衆に示す、このギロチン台上の処刑人は、そのような事実を知らな
ければ、我々は残虐な革命のシンボルのように見てしまうだろう。しかし、実は、そのシンボル
が王党派で、この処刑の後、ある司祭のもとにルイ16世の霊の鎮魂ミサを匿名で依頼して
いるような男であると、誰が想像できるだろうか。(刑死者のミサは禁じられていたし、ましてや
国王のミサなど、それだけでも極刑に値する行為)
いるような男であると、誰が想像できるだろうか。(刑死者のミサは禁じられていたし、ましてや
国王のミサなど、それだけでも極刑に値する行為)
マリー・アントワネット妃の死刑が確定した時、シャルル・アンリの妻マリー・アンヌは叫んだ。
「有罪ですって ! 王妃も国王と同じように有罪ですって ! もうたくさん、私たちの手の上に、
そして子供たちの手の上に、無実の血が流れるのは、もうたくさん !」
シャルル・アンリは「血にまみれるのは、我々の手ではなく、それを命令した者たちの手だ。彼ら
は人類に対して、また神に対して、その償いをしなければならない」と返した。
しかし妻は納得しない。
「お見事な線引きだこと、シャルル。王様の処刑の日の私の苦しみをあなたが知っているなら、
今度のさらなる殺人には手は貸さないでしょうに」
今度のさらなる殺人には手は貸さないでしょうに」
王室擁護の会話だけでもギロチン刑が確定するような恐怖政治(テルール)のパリなのだが、
執行人とその妻がこのようなシトワイアンとシトワイエンヌだったのだ ! (革命下パリでは〇〇
市民、〇〇女市民と呼び合っていた)
執行人とその妻がこのようなシトワイアンとシトワイエンヌだったのだ ! (革命下パリでは〇〇
市民、〇〇女市民と呼び合っていた)


息子Henri Sanson(人形だが) 庭園から臨むチュイルリー宮殿(1770頃) 宮殿建物は1871年焼失
そのせいか、シャルル・アンリは、王妃の処刑の執行は息子のアンリに委ねることになる。
彼は本当に心底ギロチン嫌いだったのだ。
マリー・アントワネットが最後に見たのは、チュイルリーの庭園入口近くに設置されたギロチン
台から推測すると恐らく、庭園向こうに見えるチュイルリー宮殿の眺めであった。革命通り(現
ロワイヤル通り)から革命広場(現コンコルド広場)に入る護送車の後部に後ろ向きに座っていた
ロワイヤル通り)から革命広場(現コンコルド広場)に入る護送車の後部に後ろ向きに座っていた
王妃からすると右手になる。
護送車が停車すると、王妃は誰の手も借りずに降り立つ。その顔色は蒼白だった。
処刑人シャルル・アンリ・サンソンは声を掛ける。
「お気を確かに、マダム」
王妃は穏やかに応えた。
「ありがとう、ムシュー」
オーストリア女(王妃のこと)に対する罵詈雑言が四方から浴びせられている中で、このような
優しい言葉のやりとりが、処刑人と王妃の間で交わされていたとは誰が想像しようか。
優しい言葉のやりとりが、処刑人と王妃の間で交わされていたとは誰が想像しようか。
|
