�p���ŋC�܂܂Ȑ������̌��������l�E���q�����͎��`�u�˂ނ�p���v�̒��ł�������Ă�
��B
��B
�u��������A�A���[���Ƃ��A�x�b�N�E�N�[�V�F(�ꏏ�ɐQ��)�Ƃ��A���팾�̂悤�Ɍ������炵�Ă���
�p���̐l�����́A����ɏ��a���Ă���G�g�����W�F���܂߂āA�悻�̌���ڂɂ͂������A�F�
�Ȃ̂ł͂Ȃ����Ǝv����قǂł������v
�p���̐l�����́A����ɏ��a���Ă���G�g�����W�F���܂߂āA�悻�̌���ڂɂ͂������A�F�
�Ȃ̂ł͂Ȃ����Ǝv����قǂł������v
�j�Ə��̂��ƂɊւ��ẮA���̂��������킸�����w�I�̈悾����A����قǂ̈Ⴂ�͂Ȃ�
���̂Ǝv�����A�����╶���̒��ɁA�����̎����邩�A�y�邩�A���邢�͗�^���邩�A�d
�邩�̕ʂ͂��邩���m��Ȃ��B
���̂Ǝv�����A�����╶���̒��ɁA�����̎����邩�A�y�邩�A���邢�͗�^���邩�A�d
�邩�̕ʂ͂��邩���m��Ȃ��B
���̓_�A�t�����X�Ȃǂ́A��҂̍����ɑ����邱�Ƃ͖��l�̔F�߂�Ƃ��낾�낤�B

 �@�@
�@�@
 �@�@�@�@
�@�@�@�@�@���j�I�Ɍ��Ă��A�����ւ̏�ɂ�������͑����A���ꂪ�܂����Ƃ̖��^�����E����悤
�ȑ厖���̉A�ɁA�u�A���[���v�̊����p�A�������͂��̋t�A�����̊����p�������炳�܂�
�͂��炢�Ă����肷��B
�ȑ厖���̉A�ɁA�u�A���[���v�̊����p�A�������͂��̋t�A�����̊����p�������炳�܂�
�͂��炢�Ă����肷��B
�@���j�Ƃ������ꂵ���������g���ƁA������������Ȑ��E���v���`����邪�A���F�͗��j�Ȃ�
�͐l�̏��Ƃ̒~�ςł���A���́u�l�v�Ƃ������̂́A�ǂ��炩�ƌ����ƁA�P�������Ȋ������
����A�����̐�������s���̏W�听���A�����Ȑ��E�ł���悤�͂����Ȃ��B
�͐l�̏��Ƃ̒~�ςł���A���́u�l�v�Ƃ������̂́A�ǂ��炩�ƌ����ƁA�P�������Ȋ������
����A�����̐�������s���̏W�听���A�����Ȑ��E�ł���悤�͂����Ȃ��B
�@���ۂɃX�|�b�g�����Ă�Ə�����j�_���R�ƂȂ邪�A�u�l�v�ɃX�|�b�g�����Ă�u�����A�Ȃ�
���v�ƂȂ�B
���v�ƂȂ�B
�@�F����l�I����̖��ȂǁA�l�̐l����ł�����̂ŁA����ł����ʂ��o�Ă��܂��A��
��͗��h�ȁu���j�v�Ȃ̂ł���B
��͗��h�ȁu���j�v�Ȃ̂ł���B

�@1610�N4��29���A�t�����X�����A�����S���̓X�y�C���̃t�����h���n��(���̃x���M�[�ӂ�)��
�̏o����鍐�A�t�����X�E�X�y�C���������J��Ƃ������u�������B
�̏o����鍐�A�t�����X�E�X�y�C���������J��Ƃ������u�������B
�@����͓��n���̃N���[���ƃW�����G�̗̒n�p�����Ƀt�����X���������A�X�y�C���̗̓y
�g��̖�]�ɐ^��������Ό�����R���s���ł���ƁA�ƃt�����X�̋��ȏ��ɂ͑ދ��ȋL�q��
�Ȃ���Ă���B
�g��̖�]�ɐ^��������Ό�����R���s���ł���ƁA�ƃt�����X�̋��ȏ��ɂ͑ދ��ȋL�q��
�Ȃ���Ă���B
�@�Ƃ��낪�A�����̂��̃t�����X�����A�����S���̑��߂����́A�N�ЂƂ�Ƃ��Ă���ȑ�`����
����z���̗��R���Ǝv���Ă��Ȃ��B
����z���̗��R���Ǝv���Ă��Ȃ��B
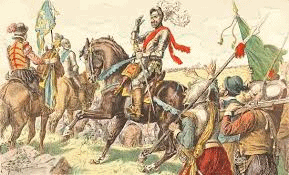
�@����11���̌R����1��2��̌R�n�A100��̖C���������ꂽ�R���s���̖{���̗��R�́A����
�}���[�E���f�B�V�X���Â����ӓ��Ղ̎��T�ɃA�����������ՐȂ������Ƃ���n�܂��Ă���E�E�E�E�B
�}���[�E���f�B�V�X���Â����ӓ��Ղ̎��T�ɃA�����������ՐȂ������Ƃ���n�܂��Ă���E�E�E�E�B

�@���܂͉��̖ڂۗ̕{�ɂƁA�{��̗����̔����������W�߂��o���[���㉉�������B���̔�
�������̒��ɁA14�̃V�������b�g�E�h�E�����������V�[�삪�����B
�������̒��ɁA14�̃V�������b�g�E�h�E�����������V�[�삪�����B
�u�����������Ƃɖ��S�Ȏ҂̐S�܂ł��߂炦���v�Ɠ����̋L�^�ɂ�����ʂ�A���̋����̔���
���̖��͍͂ۗ����Ă���A�A�������͂����ǂ���ɖ�������Ă��܂��B
���̖��͍͂ۗ����Ă���A�A�������͂����ǂ���ɖ�������Ă��܂��B
 �@
�@
�@���͔ޏ����t�����\���E�h�E�o�b�\���s�G�[���ƍ��ł���ƒm��ƁA�����ł����������
���A���I�|���҂Ƃ��Ė������R���f���݂ƌ���������悤��z�����B
���A���I�|���҂Ƃ��Ė������R���f���݂ƌ���������悤��z�����B
�@��������A�ޏ����v���悤�Ɉ͂��邩�炾�B
�@�@
�@�����č����͔M��ȃA�v���[�`��ޏ��ɌJ��Ԃ����B�����������V�[��̕��ł́A���̍���
�̍D�F�ȗ~���ɂ͂܂��������肵�Ă���A���̎v�������ɏ]������ɂȂ�Ȃ��B����������
����ɁA���ɖ��S�Ȃ͂��̕v�N�R���f���݂����̖��f�I�Ȏ�Ȃɂ������ꂱ��ł���
�����B
�̍D�F�ȗ~���ɂ͂܂��������肵�Ă���A���̎v�������ɏ]������ɂȂ�Ȃ��B����������
����ɁA���ɖ��S�Ȃ͂��̕v�N�R���f���݂����̖��f�I�Ȏ�Ȃɂ������ꂱ��ł���
�����B
�@�����Ō��݂͋{��������Ď����̗̒n�ɏZ�݂����|��t�シ�邪�A����Ȑ\���o�Ȃǎ�
�������͂����Ȃ������B
�������͂����Ȃ������B

�@�����̂˂������������ɍ���ʂĂ��ȁA���i�ɋꂵ�ޕv�E�E�E�E
�@��₠���āA���̓�l�͂��ɍ��O�ɓ��S�Ƃ������s��i�ɂ���������B
�@�t�����h���̎i�ߊ��A���x�[������̂��Ƃ֓������킯�����A�����̓X�y�C���̂Ȃ̂�
�S���ɓ������B�����ɃA�������͎g�҂Ƃ��ăv��������݂�h���A�R���f���ݕv�Ȃ̐g���̈�
�n�����A���x�[������ɗv������B�������A����͂��������B
�S���ɓ������B�����ɃA�������͎g�҂Ƃ��ăv��������݂�h���A�R���f���ݕv�Ȃ̐g���̈�
�n�����A���x�[������ɗv������B�������A����͂��������B
�@�����͑S�t������O�ɏ��W�B
�u�X�y�C���ɐ��z�����B�ǂ������Ă��A�R���f�̏��[�ɉ�����̂��v�Ɗ���@��������
�ł���B
�@�������āA�t�����X�R�̓t�����h���ւ̐i�U���J�n�����B

�E�E�E�E�������A���̗����A�A�����S���͋��M�҃����@�C���b�N�ɈÎE����A���͓ڍ��B��
�@�s���̂��̐푈�͍K���ɂ��ďI�����������E�E�E�B
�@���Ƃ��Ƃ��V���k(���O�m�[)���狌���k(�J�g���b�N)�ɏ@�|�ς������A���������������A���̓x
�̌R���s���́A�h�C�c�̐V���k���͂Ƃ̘A�g�̂��ƂɃJ�g���b�N�ł���X�y�C�����ւ̐i�U��
��ł��������߂ɁA�M��ȃJ�g���b�N�̏C���m�����@�C�A�b�N�́A�u���Ȃ�d���v�Ƃ��ăA�����S��
���ÎE�����̂ł���B
�̌R���s���́A�h�C�c�̐V���k���͂Ƃ̘A�g�̂��ƂɃJ�g���b�N�ł���X�y�C�����ւ̐i�U��
��ł��������߂ɁA�M��ȃJ�g���b�N�̏C���m�����@�C�A�b�N�́A�u���Ȃ�d���v�Ƃ��ăA�����S��
���ÎE�����̂ł���B

�@�ꃕ����A�R���f���ݕv�Ȃ͋A�����A�K���Ȍ��������������B
�@�Ȃ��A���j�̗����ς������̎h�q�����@�C�A�b�N�����A��q�̍����ÎE�ɂ͗��H���R
���闝�R������킯�����A�^�������ЂƂ͂����肵�Ȃ��̂������炵���B

�@�l�X�Ȑ��̒��ɁA�����A�������ɗU�f���ꂽ���Q����A����Z���̓�˂��Ŏh�E�����Ƃ���
���̂�����B�������ꂪ�^���Ȃ�A���j�������Ɏ���Ő��藧���Ă��܂�������������
�肾�B
���̂�����B�������ꂪ�^���Ȃ�A���j�������Ɏ���Ő��藧���Ă��܂�������������
�肾�B
�@���������ɐ푈���n�܂�A�l�I���݂ō������ÎE�����B.....�Ȃ�Ƃ������h�ȗ��j�ł�
��B
��B

�@1627�N�A�t�����X�̐V���k�̉��Ƃ������郉�E���V�F�����A�V�����C�M���X�̊͑��h���Ƃ�
����|����Ȏx���̂��ƕ����I�N�����B�O�q�̃A����4���̎q���C13���ƃ��V�������[�ɑ��͎�
��R�𗦂��Ă��̒����������B�C�M���X���炷��Α嗤�i�U�ւ̑�������ƁA���@�h�̐l�X
���x������Ƃ�������ł�����A�C�M���X�̍ɑ��o�b�L���K�����݂�5��̌R���𗦂��ăt����
�X�̓��ɏ�荞��ł����B
����|����Ȏx���̂��ƕ����I�N�����B�O�q�̃A����4���̎q���C13���ƃ��V�������[�ɑ��͎�
��R�𗦂��Ă��̒����������B�C�M���X���炷��Α嗤�i�U�ւ̑�������ƁA���@�h�̐l�X
���x������Ƃ�������ł�����A�C�M���X�̍ɑ��o�b�L���K�����݂�5��̌R���𗦂��ăt����
�X�̓��ɏ�荞��ł����B
�@�t�����X�Ƃ��ẮA�����@���푈�̉ʂĂɂ悤�₭�V���k�M���̎�̂𖡕��Ɉ�������āA
�������������É����Ă������̔����Ƃ����āA���ʂ����ẴC�M���X�Ƃ̑Ό��̗l����悵
�Ă������̌R���s���ɉ����̈АM�������ėՂB
�������������É����Ă������̔����Ƃ����āA���ʂ����ẴC�M���X�Ƃ̑Ό��̗l����悵
�Ă������̌R���s���ɉ����̈АM�������ėՂB
�@�X�y�C�������͓����J�g���b�N�����Ƃ��ăt�����X�x���̊͑���h������B
�@�������āA�v���e�X�^���g�ƃJ�g���b�N�̗����̏@���I�����ƍ��Ɨ��Q�̏Փ˂��A���̃��E���V�F
���̒���ɓW�J�����B
���̒���ɓW�J�����B
�E�E�E�������A��������1��5����̏Z���̋]��������Ɋח����邱�ƂɂȂ郉�E���V�F���̐V
���k�����́A����Ȑ��ʂ�������_�ȑ呛���������N��������͂Ȃ������B
���k�����́A����Ȑ��ʂ�������_�ȑ呛���������N��������͂Ȃ������B
�@�C�M���X���ނ�ƃt�����X�����Ƃ̏����荇���ɕ֏悵�đ�|����Ȑ푈���n�߂��܂ł̂���
�Ȃ̂��B���̃C�M���X�̍����`���[���Y1���́A�ɑ��̃o�b�L���K�����݂̔M��Ȑ����̖���
����̏o�������ӂ����炵���B
�Ȃ̂��B���̃C�M���X�̍����`���[���Y1���́A�ɑ��̃o�b�L���K�����݂̔M��Ȑ����̖���
����̏o�������ӂ����炵���B

�@�����Ă��̃o�b�L���K�����݂́u�M��Ȑ����v�̐^�ӂ́A�ʂ����Ė{���ɁA�C�M���X�̍��Ɨ�
�v�Ȃ̂��A���邢�͐V���k�̓��E�~�ςƂ����@���I�M��Ȃ̂��B
�v�Ȃ̂��A���邢�͐V���k�̓��E�~�ςƂ����@���I�M��Ȃ̂��B
�@�Ƃ�ł��Ȃ��A�ނ̖ړI�͂܂������ʂ��B�C�L���X�ɑ��Ƃ��Ă̗���ł��Ȃ���A�V���k�Ƃ�
�Ă̗���ł��Ȃ��B35�̔��j�̃W���[�W�E���B���A�[�Y�Ƃ��Ă̗���A���ꂪ���ׂĂł������B
�Ă̗���ł��Ȃ��B35�̔��j�̃W���[�W�E���B���A�[�Y�Ƃ��Ă̗���A���ꂪ���ׂĂł������B
�@�ނ́A�O�C�L���X�����W�F�[���Y 1���̒��b�Ƃ��āA���́u�T�[�v�̐g������A2�N�ɂ��Ďq
�݁A���N���݈ʂ��A�X��2�N��Ɍ�݁A4�N���1623�N�Ɍ��݂ɏ�����A���{�̗v�E���C��
�Ă����B���������ꂷ�ׂč������Ĉ�(�W�F�[���Y���͓������Ŗ�����)�ɂ����̂ŁA������
�Ƃ��Ă͎��s�̘A���A�c��̒e�N���邱�Ƃ������������B
�݁A���N���݈ʂ��A�X��2�N��Ɍ�݁A4�N���1623�N�Ɍ��݂ɏ�����A���{�̗v�E���C��
�Ă����B���������ꂷ�ׂč������Ĉ�(�W�F�[���Y���͓������Ŗ�����)�ɂ����̂ŁA������
�Ƃ��Ă͎��s�̘A���A�c��̒e�N���邱�Ƃ������������B
�@�������A����������A���e�ɂ��b�܂�Ă������̌��݂́A�����𖣗�����ˊo�͓��㐏���
����B
����B
 �@
�@ �@
�@
�@�@�t�����X�������C13���@�@�@�@�@�����A�����G�b�g�E�}���[�@�@�C�M���X�����`���[���Y1��
�@�ނ�1625�N�A���C13���̖��N�ƃC�M���X���`���[���Y�̍��V�𐮂���ړI�Ńt�����X��K��
��B�����ă��C13���̂��܃A���k�E�h�[�g���b�V���Əo������B���̔��������܂́A�������|�NjC
���̕v�N���C���ɑa���Ă���A�فX�ƈٍ�(�ޏ��̓X�y�C����������ł���)�̊���Ő�
���������B
��B�����ă��C13���̂��܃A���k�E�h�[�g���b�V���Əo������B���̔��������܂́A�������|�NjC
���̕v�N���C���ɑa���Ă���A�فX�ƈٍ�(�ޏ��̓X�y�C����������ł���)�̊���Ő�
���������B
�@�@�@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
 �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�@�@�@�t�����X���܃A���k�E�h�[�g���b�V���@�@�@�@�@�@�@�A���k���܂ƃC�M���X�ɑ��o�b�L���K����
�@���̔ޏ��̑O�ɓo�ꂵ���o�b�L���K�����݂́A�����U�����D��ȑf�G�ȃW�F���g���}���ŁA
�₵���ޏ��̐S��V�N�ȗ��̖����ɖ������Ă����B
�₵���ޏ��̐S��V�N�ȗ��̖����ɖ������Ă����B
�@���݂̕����A���k���܂ɂ������薣������A�O�����ȂǖY��āA���̃A���@���`���[����
�����ɂȂ����B
�����ɂȂ����B
 �o�b�L���K�����ƃA���k����
�o�b�L���K�����ƃA���k�����@���܂̑��߂������A��l���݂��̏�M���m�F�������@���^���悤�Ƃ��������̂ŁA��
�̃t�����X���܂ƃC�M���X�ɑ��̊W�͂������҂�ɂȂ��Ă��܂����B
�̃t�����X���܂ƃC�M���X�ɑ��̊W�͂������҂�ɂȂ��Ă��܂����B


���[�x���X



���̏ё��悪�`���ꂽ�̂�1625�N�����A���[�x���X�͌�����̕ǂ̒����Ƀo�b�L���K���̏ё��炵�����̂�`��
����ł���Ƃ����ʔ�����������B�{���Ȃ��͂�]���̃X�L�����_���������̂��낤�E�E�E
����ł���Ƃ����ʔ�����������B�{���Ȃ��͂�]���̃X�L�����_���������̂��낤�E�E�E
�@���X�̉�z�^�ɂ�����A�㐢�Ɂu�����v�Ƃ��ē`�����A���́u�O�e�m�v�̒��ł����̓�l
�̐��I�̗����A�d�Ɨ���ŕ����i�߂Ă���̂͗L�����B(���E���V���t�R�[���݉�z�^�ɋL
����Ă���A���k���܂ƃo�b�L���K�����݂̃_�C���̏��蕨�����ɂ��ẮA�u�f�G�Ŏj�I��
�O�e�m�v�~���f�B�̍����Q��)
�̐��I�̗����A�d�Ɨ���ŕ����i�߂Ă���̂͗L�����B(���E���V���t�R�[���݉�z�^�ɋL
����Ă���A���k���܂ƃo�b�L���K�����݂̃_�C���̏��蕨�����ɂ��ẮA�u�f�G�Ŏj�I��
�O�e�m�v�~���f�B�̍����Q��)

��l�̗��H�̓t�����X�ɑ����V�������[�̌�����������B���̃t�����X��Ή����m���̗�
���҂Ō��i�ɂ��Ĕ��Ȑ����ƃ��V�������[�́A���̎��A�A���k���܂��t�����X�����̗��Q�ɂ�
���Ċ댯�Ȑl���Ƃ��Ĕc�����Ă����B
���҂Ō��i�ɂ��Ĕ��Ȑ����ƃ��V�������[�́A���̎��A�A���k���܂��t�����X�����̗��Q�ɂ�
���Ċ댯�Ȑl���Ƃ��Ĕc�����Ă����B
�E�E�E�ƁA�N�����l���邾�낤�B
�@�m���ɁA���܂ɑ��ĕ����Ă����͎̂������B���������̕���̐^�̓��@�́A�t�����X����
���Ƃ��Ă̂��̂��ǂ����͋^�킵���B�����ł��A�܂��A�ނ��A���}���E�W�����E�f���E�v���V�Ƃ�����
�l�̒j�Ƃ��Č��˂Ȃ�Ȃ��B
���Ƃ��Ă̂��̂��ǂ����͋^�킵���B�����ł��A�܂��A�ނ��A���}���E�W�����E�f���E�v���V�Ƃ�����
�l�̒j�Ƃ��Č��˂Ȃ�Ȃ��B

�@�����̎���ʂ̃^���}���E�f�E���I�[�ɂ��A���V�������[�͍����̌��N���(���܂Ƃ̊�
�Ɏq���������悤�Ƃ��Ȃ�)��J���A���̂܂܂ł͎������ʂ͉���K�X�g���̂��̂ƂȂ�A������
�n�ʂ�������Ɗ�䂵�A�����S�߂ȗ��ꂪ�\�z����鉤�܃A���k�Ǝ��g�݁A����̎�Ŏq
��������������A���Ƃ̈��ׂ�}�낤�A�ہA�d�낤�Ƃ����A�Ƃ����B
�Ɏq���������悤�Ƃ��Ȃ�)��J���A���̂܂܂ł͎������ʂ͉���K�X�g���̂��̂ƂȂ�A������
�n�ʂ�������Ɗ�䂵�A�����S�߂ȗ��ꂪ�\�z����鉤�܃A���k�Ǝ��g�݁A����̎�Ŏq
��������������A���Ƃ̈��ׂ�}�낤�A�ہA�d�낤�Ƃ����A�Ƃ����B
 �@�@����K�X�g���@
�@�@����K�X�g���@
�@�����Ĕނ͉��܂̑��߂�ʂ��Đڋ߂��Ă���B����́A���Ƃ̈��ׂƂ��Ȃ̐g�̕ۑS�Ƃ���
���ڂɒj�Ƃ��Ă̏�~�������������ǂȓ��@�ł��邪�A����������O���킵�Ă���B
���ڂɒj�Ƃ��Ă̏�~�������������ǂȓ��@�ł��邪�A����������O���킵�Ă���B
�@����ȕs���N�ȉ��͂����ɕ��䂷��A���܂������̎q��g������A���ꂪ���ʂ��p������
�A�ɑ��Ƃ��ĕ��Ƃ��Đe�g�ɐ����ɗ�߂�B�������A����Ȗڏo�x�����z��������̂��B�ނ�
���͋{��ٔ��������ǂ܂�A��͖̑������B����Ȍ������Ƃɍ�����ȂǂƂ������z
�́A���C�̍����ł���B
�A�ɑ��Ƃ��ĕ��Ƃ��Đe�g�ɐ����ɗ�߂�B�������A����Ȗڏo�x�����z��������̂��B�ނ�
���͋{��ٔ��������ǂ܂�A��͖̑������B����Ȍ������Ƃɍ�����ȂǂƂ������z
�́A���C�̍����ł���B
�@�������A���̋��C�A���Ȃ������蓾�Ȃ����Ƃł��Ȃ��̂�.....�B

�@�f���E�v���V�Ƃ͐��_��Q�̌X�����������B�ނ̌Z�A���t�H���X�͎������_�ł���ƐM����
�����B�����Ĕނ̖��u���[��ݕv�l�́A�����̑̂��K���X�ŏo���Ă���Ǝv�����݁A�����č�
�낤�Ƃ��Ȃ������B����ȌZ�����������ނ����X���m�Ȕ��z�ɂƂ��ꂽ�Ƃ��Ă��d�����Ȃ��A
�Ƃ����������ł���B(�]�k1)
�����B�����Ĕނ̖��u���[��ݕv�l�́A�����̑̂��K���X�ŏo���Ă���Ǝv�����݁A�����č�
�낤�Ƃ��Ȃ������B����ȌZ�����������ނ����X���m�Ȕ��z�ɂƂ��ꂽ�Ƃ��Ă��d�����Ȃ��A
�Ƃ����������ł���B(�]�k1)
�@�Ƃ������A�ނ́A�A���k���܂ɂ���Ȗژ_�����������ڋ߂��A��_�ɋ��������B
�@�������A���܂͔ނ���ɋ������s�G���Ƃ��Ě}�����܂łŁA���̂Ƃ�ł��Ȃ��A�v���[�`����
�R����B
�R����B
�@�j�Ƃ��Ă̖̑ʂ�傢�ɏ�����ꂽ���V�������[�ɑ��́A���̏��������X�����܂܁A�p�b�L
���K�����݂Ɖ��܂Ƃ̃X�L�����_���ɐڂ����킯�ł��邩��A������傢�ɍ�p���Ă̑Ή���
�Ȃ�B
���K�����݂Ɖ��܂Ƃ̃X�L�����_���ɐڂ����킯�ł��邩��A������傢�ɍ�p���Ă̑Ή���
�Ȃ�B
�@�p�b�L���K���͋A���̌�A�A���k���܂ւ̗���߂�炸�A���̌�ɍĂуt�����X��g
�Ƃ��ĕ����߂낤�ƃ`���[���Y���ɐ\�������B�Ƃ��낪�A���V�������[�̓��C���ɑ�g����
�����₷��悤����A�t�����X�����͐����Ƀo�b�L���K�����݂̓n���̋��ۂ�\������B
�Ƃ��ĕ����߂낤�ƃ`���[���Y���ɐ\�������B�Ƃ��낪�A���V�������[�̓��C���ɑ�g����
�����₷��悤����A�t�����X�����͐����Ƀo�b�L���K�����݂̓n���̋��ۂ�\������B

�@�o�b�L���K���͗���ɋ����A�����Ȃ��̓p����������s���邵����͂Ȃ��ƌ��āA��i���
���B���x�A���E���V�F���������̗v�ǂ��߂����ăt�����X�����Ɩ㒅���N�����Ă�����ɐڂ�
���A�C�M���X�Ƃ��Ă͓����V���k���������ׂ��ł���ƃ`���[���Y���ɋl�ߊ��A�u����v��
�����ɉ����R��g�D�A����w���ɗ����Ă̏o�w�Ƒ��������B
���B���x�A���E���V�F���������̗v�ǂ��߂����ăt�����X�����Ɩ㒅���N�����Ă�����ɐڂ�
���A�C�M���X�Ƃ��Ă͓����V���k���������ׂ��ł���ƃ`���[���Y���ɋl�ߊ��A�u����v��
�����ɉ����R��g�D�A����w���ɗ����Ă̏o�w�Ƒ��������B
�@���ꂪ�A���̃��E���V�F���̍U�͐�̐^���炵���B
�@�퓬���ɕߗ��ƂȂ��ăo�b�L���K���̑O�ɘA�s���ꂽ�T���E�Z�����@���a�́A�ނ̐Q��̂�
���T��ɃA���k���܂̏ё��悪�����Ă���̂�ڌ����Ă���A���܂��Ƀ��V�������[�w�̓`����
���܂�Ă���B
���T��ɃA���k���܂̏ё��悪�����Ă���̂�ڌ����Ă���A���܂��Ƀ��V�������[�w�̓`����
���܂�Ă���B
�@���̓��e�́A�������t�����X��g�Ƃ��Ď���Ă����A���E���V�F������P�ނ��邵�A��
�t�����X������~����Ƃ������̂ł������B
�t�����X������~����Ƃ������̂ł������B
�@�T���E�Z�����@���a�͎ߕ�����A���̐\���o�����V�������[�ɓ`�����Ƃ���u����ȏ�b������
����͂˂�v�ƌ��������ς˂�ꂽ�Ƃ����B
����͂˂�v�ƌ��������ς˂�ꂽ�Ƃ����B

�@���ǁA���̐�̓C�M���X�R�̓P�ނƁA���E���V�F���̊J��ɏI���A�o�b�L���J���̗��̖�]
�͋��U�����B
�͋��U�����B
�@�������ނ͂��̌�\�����ɓn���đ�D�c��g�D�A�Ăуt�����X�w��荞�ޏ�����T�d�ɂ���
�߂��B���Ȃ�Ȏ��O�ł���B
�߂��B���Ȃ�Ȏ��O�ł���B
�@�Ƃ��낪�A�o�`�Ԓ��̔ނ̓W�����E�t�F���g���Ƃ����ꏫ�Z(���E���V�F���̃����̐�ɂ����т�
���ĎQ�����Ă���l��)�̒Z���̈ꌂ�ɓ|���B
���ĎQ�����Ă���l��)�̒Z���̈ꌂ�ɓ|���B
�@���̃t�F���g���A���̏،��ł́A�ߎS�Ȑ퓬�ł̑̌��ɔY��ł���(����̃V�F���V���b�N)��
���A�R���ł̏��i�▢�����������̌l�I�ȍ��݂Ƃ��A�܂����V�������[�̍����������h�q��
�������Ă��邪�A�Ƃ�������̍��Ƃ̐푈�����܂Ŋ����N�������o�b�L���J�����݂̃���
�X�g�[���[�͏I�����}�����̂ł������B
���A�R���ł̏��i�▢�����������̌l�I�ȍ��݂Ƃ��A�܂����V�������[�̍����������h�q��
�������Ă��邪�A�Ƃ�������̍��Ƃ̐푈�����܂Ŋ����N�������o�b�L���J�����݂̃���
�X�g�[���[�͏I�����}�����̂ł������B
 �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
1628�N8��23�����A�o�b�L���K�����͈ÎE�����B�@�@�@�@�@�@�@�@John Felton

�@���̃A���k���܂����ǂ̂Ƃ���ǂ��ɂ��q���������邱�Ƃ�������(���̐^�̕��e�����C13��
�ł��邩�A�������X�̂Ƃ���ł͂��邪)�A���C13������̌�A���C14�������ʂ���B
�ł��邩�A�������X�̂Ƃ���ł͂��邪)�A���C13������̌�A���C14�������ʂ���B
�@���ʂƂ͌����܂��c���Ȃ̂ŁA�C�^���A�o�g�Ńt�����X�ɋA�������}�U�����ɑ��ƃA���k���@
�̐ې������ƂȂ�B
�̐ې������ƂȂ�B
�@���̃}�U�����ɑ��Ƃ����j�̓o�b�L���K�����݂̖ʉe����������A�Ƃ��������Z��̐F
�j�A�܃��A���k���@�ɂƂ��Ă͐��Ɂu�^�C�v�̒j���v�ł������B
�j�A�܃��A���k���@�ɂƂ��Ă͐��Ɂu�^�C�v�̒j���v�ł������B

�@���V�������[�ɑ������łɐ��ɂȂ��A�A���k���@�͎���ꂽ�����悤�₭���߂������̂�
���ɁA�}�U�����ɑ��Ɠ�l�ʼn���������̂ł���B
�@���̃}�U�����A���V�������[�Ɠ������@���ł���A�܂�煘r�����Ƃ̃��V�������[���������]��
����Ă����j�����A���V�������[�ɑ��Ƃ͑傫�ȈႢ���������B����̓A���k���@�ƓG�����
���납�A���̂����������ǂ������_���B
����Ă����j�����A���V�������[�ɑ��Ƃ͑傫�ȈႢ���������B����̓A���k���@�ƓG�����
���납�A���̂����������ǂ������_���B
�@�閧�������܂ł��邭�炢�E�E�E�E
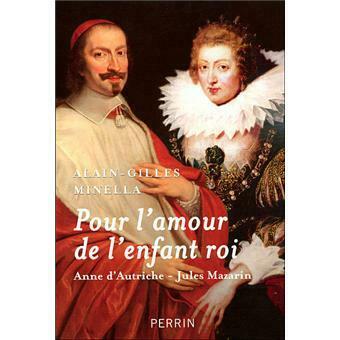 �@�@�@
�@�@�@
����ȍ����摜���\���̖{�܂ŏo�Ă�B�@�@�@1632�N�̃}�U�����̂��̏ё����Ə����o�b�L���K���Ɏ��Ă��邩�E�E�E
�@��������l�̐ې������́A�����̋M���̔������A�����ɂ͒����ł����Ă��ې����{�Ƃ�
��Ə�ɑ�_�ɔ��R���Ă���t�����X�M���̌������������Ă��܂��B���ƂɃ}�U�����ȂǂƂ����O
���̎��f�����債�����Ƃ̂Ȃ�����オ��҂��A�������������̂ł͖ʔ����Ȃ��B
��Ə�ɑ�_�ɔ��R���Ă���t�����X�M���̌������������Ă��܂��B���ƂɃ}�U�����ȂǂƂ����O
���̎��f�����債�����Ƃ̂Ȃ�����オ��҂��A�������������̂ł͖ʔ����Ȃ��B
�@�����ŁA�����@�@�Ƃ̑Η������[�Ŏn�܂��������{�̖\���ɁA�M�������͎��X�ƕ֏悵�A��
������Ă̑嗐���n�܂�B������t�����h�̗��Ƃ����B
������Ă̑嗐���n�܂�B������t�����h�̗��Ƃ����B
�@������A���j�Ƃ́u�����I��M���̍Ō�̔����������v���ƒ�`�Â��悤�Ƃ���B�Ƃ��낪��
��ł��Ȃ��B
��ł��Ȃ��B
 �@
�@
�@��d�i�̃{�[�t�H�[�����݂Ƃ������O���B�����݂Ƃ��k���\�����݂Ƃ��A���ꂼ�ꌨ������
�Ŕ��f����A����������M���ł��邪�A�ނ�͒n���ɓƗ��I�Ȍ��͂Ȃǎ����Ȃ��V���̑�
�M���A����Ή����̒��Ő��܂ꂽ�M�������ł���A�����I��M���ł����ł��Ȃ��B�����̔�
��͎���̔j�łł���A���Ȃ̂��B
�Ŕ��f����A����������M���ł��邪�A�ނ�͒n���ɓƗ��I�Ȍ��͂Ȃǎ����Ȃ��V���̑�
�M���A����Ή����̒��Ő��܂ꂽ�M�������ł���A�����I��M���ł����ł��Ȃ��B�����̔�
��͎���̔j�łł���A���Ȃ̂��B
�@���j�̗���Ƃ��ẮA���x�A��M���Ō�̔����������Ƃ����̂��s���ǂ��ʒu�Â��ł���
���A���g�͂���Ȃ��̂ł͂Ȃ��̂ł���B
���A���g�͂���Ȃ��̂ł͂Ȃ��̂ł���B

�@���H���e�[�����A�C�̌������C�M���X�l�����͖فX�Ƃ��̂�����荇���Ă���̂ɑ���(�C�L
���X�ł̓s���[���^���v���̍Œ��ō����̎�����)�A�t�����X�l�͖ʔ������A���Ȃ����
�����N�������A�Ƃ��̃t�����h�̗����R�P�ɂ���B
���X�ł̓s���[���^���v���̍Œ��ō����̎�����)�A�t�����X�l�͖ʔ������A���Ȃ����
�����N�������A�Ƃ��̃t�����h�̗����R�P�ɂ���B
�@�m���ɁA�p���͑呛���ŁA�h��Ƀh���p�`����炩���A�{��̓p�����o�������A��������
�Ŕ�����F�d�|���̘U����炪��ǂ���ς����A�������ɂ��ׂĂ��Ƃ̂܂܂ō������ꂽ��
���B
�Ŕ�����F�d�|���̘U����炪��ǂ���ς����A�������ɂ��ׂĂ��Ƃ̂܂܂ō������ꂽ��
���B
�@���F�Ƃ��Ă�������̂́A�����������Ȃ�h��h�肵�����A�����̎哱���������Ă���
���Ƃł��낤�B
���Ƃł��낤�B

�@�`���ɏЉ���A�V��4�����M��ɗ������������V�������b�g�E�h�E�����������V�[�̖������O
���B�����ݕv�l�́A�قƂ�ǎ���ƌ����Ă����������Ȃ��B
���B�����ݕv�l�́A�قƂ�ǎ���ƌ����Ă����������Ȃ��B

�u⼌��^�v�Ŗ������N�l���E���V���t�R�[���݂́u�����O���B���v�l�̔������A�@�m�A�l���S�̂�
���͈͂������ŁA���̐l�̂��߂Ȃ�ǂ�Ȃɋꂵ��ł������v�Ɛ�^���A����_�A�ނ͗�
��̉��Ƃւ̒��߂����Ȃ���̂āA���R�̊����ɗ������ޏ��ɏ]���Đ킢�A�A���Ƃɒe�ۂ�
�ĕ�������ď�ԂɊׂ�̂��B���ɋ������N�l�Ƃ����킯���B
���͈͂������ŁA���̐l�̂��߂Ȃ�ǂ�Ȃɋꂵ��ł������v�Ɛ�^���A����_�A�ނ͗�
��̉��Ƃւ̒��߂����Ȃ���̂āA���R�̊����ɗ������ޏ��ɏ]���Đ킢�A�A���Ƃɒe�ۂ�
�ĕ�������ď�ԂɊׂ�̂��B���ɋ������N�l�Ƃ����킯���B
 �@
�@
�@�܂��A���̓����A�t�����X�R�̎i�ߊ��Ƃ��ăR���f����(�����O���B���v�l�̒�)�ƃ`�������k��
���̓�l�������̗_�ꍂ���A�l�X�̐M�]����Ă������A��҃`�������k�����́A�E���A��
���ƂƂ��Ĉ̐l�̗ނ��ł������B�Ƃ��낪�A���̈̑�Ȃ錳���A�����u�������A�X�y�C�����
�ɂ���A����������Ă������A�����O���B�����ݕv�l�̐F�d�|���̗U���ɂ܂�܂Ƃ͂܂�A��
�ƁA������Ȃ������Ĕ����R�ɑ������̂��B������͗��ɋ����������Ƃ����킯���B
���̓�l�������̗_�ꍂ���A�l�X�̐M�]����Ă������A��҃`�������k�����́A�E���A��
���ƂƂ��Ĉ̐l�̗ނ��ł������B�Ƃ��낪�A���̈̑�Ȃ錳���A�����u�������A�X�y�C�����
�ɂ���A����������Ă������A�����O���B�����ݕv�l�̐F�d�|���̗U���ɂ܂�܂Ƃ͂܂�A��
�ƁA������Ȃ������Ĕ����R�ɑ������̂��B������͗��ɋ����������Ƃ����킯���B

�@�܂��k���y�����k�̑��h�b�J���N�[�������́A��͂蔽���R�̏���d�҃����o�]�����ݕv
�l�Ɂu�y�����k�́A���ɂ��킵�����̐l�̂��́v�Ǝ莆�𑗂���A�t�R�̏��ƂȂ�B
�l�Ɂu�y�����k�́A���ɂ��킵�����̐l�̂��́v�Ǝ莆�𑗂���A�t�R�̏��ƂȂ�B
 �@�@�@�@�@
�@�@�@�@�@ �@
�@
Duchesse de Montbazon �@�@�@�@�@Duchesse de Chevreuse �@�@ Duchesse de Chatillon
�@�܂����[�O��݂̓V�������[�Y���ݕv�l�̗��l�Ƃ��Ĕ����R�ɎQ���A �g�D�[�����B�����ݗ�
��̓v�[�g���B���A�����N�T���u�[���A�o���e�[�A�����[�h�Ȃǂ̏�����F���Ō��f�A���R��
�Ɉ������ꂽ�B�܂��A���R�̏��ł���v���펀�����V���e�B�������ݕv�l�͔����R�̃k���[��
���݂₻�̋`�Z�̃{�[�t�H�[�����݂̈��l���������A�`�Z�퓯�m������������g���u������
���N�����A�k���[�����݂������B(�]�k2)
��̓v�[�g���B���A�����N�T���u�[���A�o���e�[�A�����[�h�Ȃǂ̏�����F���Ō��f�A���R��
�Ɉ������ꂽ�B�܂��A���R�̏��ł���v���펀�����V���e�B�������ݕv�l�͔����R�̃k���[��
���݂₻�̋`�Z�̃{�[�t�H�[�����݂̈��l���������A�`�Z�퓯�m������������g���u������
���N�����A�k���[�����݂������B(�]�k2)
�@�Ⴆ�A�C�^���A�o�g�̍ɑ��ƃX�y�C���o�g�̑��@�Ƃ̐ې������Ƃ͌����A����������������
���鐳���Ȑ��{�ł��邱�ƂɈႢ�͂Ȃ��B����ɋ|���Ђ��Ƃ������Ƃ͑�t�̏d�߂ł���B����
������ɖ�����ꂽ�Ƃ͌����A���Ƃ�ׂ������m��ʖ��q���̍s�ׂȂ̂ł���B�ɂ�������
�炸�A�����������̖���M���炪�A�F���ɕ�����āA�v�����ʂ������Ƃ����̂͋��قł���B
���鐳���Ȑ��{�ł��邱�ƂɈႢ�͂Ȃ��B����ɋ|���Ђ��Ƃ������Ƃ͑�t�̏d�߂ł���B����
������ɖ�����ꂽ�Ƃ͌����A���Ƃ�ׂ������m��ʖ��q���̍s�ׂȂ̂ł���B�ɂ�������
�炸�A�����������̖���M���炪�A�F���ɕ�����āA�v�����ʂ������Ƃ����̂͋��قł���B
�@����ȃV�����\���̉̐����������Ă��������B
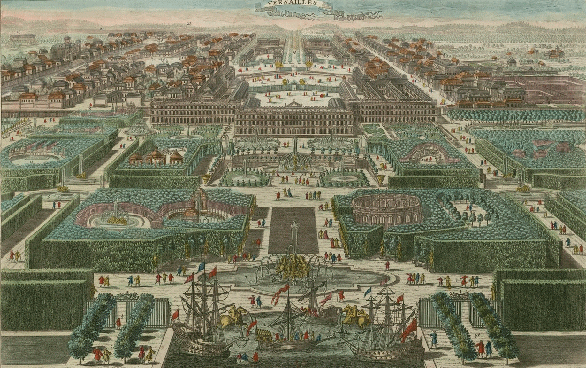
�@�@�@ �@
�@
 �@
�@
�@�t�����h�̓��������A�c���ł��������C14���͂����܂����������A�t�����X�����[���b�p�̈ꗬ
���Ɏd���Ă�����B�R���I�ɂ��A�����I�ɂ��A���ׂă��F���T�C���𒆐S�Ƃ��đS�����O����
���B
���Ɏd���Ă�����B�R���I�ɂ��A�����I�ɂ��A���ׂă��F���T�C���𒆐S�Ƃ��đS�����O����
���B
�@���F���T�C���̉h�s�h�̒��A���C14���͗l�X�ȋ{��G�������o���A�N������V�N
�Ɏ���܂Ő��̐��قǂ̏����������ނ̐l������������P�ōʂ����B




�@Olympe Mancini�@�@�@Marie Mancini�@�@�@�@�@�@�@de la Mothe-Houdancourt�@�@�@Henrietta Anne Stuart





�@�@�@de La Valliere�@�@�@�@ �@�@�@d'Heudicourt�@�@�@�@�@de Gramont�@�@�@�@de Montespan�@�@�@�@�@de Thianges




�@�@de Rohan-Chabot�@ �@ �@�@�@�@�@de Maintenon �@�@ �@�@�@�@des Osillets �@�@�@�@�@�@�@�@�@ de Fontanges
�@�}�V�V�j�Ƃ̗ߏ삽���A���E���@���G�[����A�����e�X�p����ݕv�l�A�t�H���^���W����A����
�ă}���g�m���v�l�A���̑��̑��̊Ԃ̗��̃q���C�������E�E�E�B(�Ԏ��͗L��)
�ă}���g�m���v�l�A���̑��̑��̊Ԃ̗��̃q���C�������E�E�E�B(�Ԏ��͗L��)
�@��࣍��ȃ��F���T�C���{�a�̗����G���͂����Ƃ��悤�B��̃��C14�����������̏ё���Q
�̒��ɂ́A�����h����ݕv�l�̂悤�ȗ��̏ё������Ȃ����̂͏����Ă��邵�A�܂������̈��l
����������Ƃ͑z���ɓ�Ȃ��B
�̒��ɂ́A�����h����ݕv�l�̂悤�ȗ��̏ё������Ȃ����̂͏����Ă��邵�A�܂������̈��l
����������Ƃ͑z���ɓ�Ȃ��B
�@�܂������̏��������̒��ɂ͑��̊Ԃ̂�������܂܂�邵�A���������Ƃ��Č������ւ���
����������B
����������B
 �@�@�@
�@�@�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@Hortense Mancini�@�@�@ �@ Charles II
�@�Ⴋ���C���𖣗������ŏ��̓�l�̃}���V�j��͎o���ł���B5�l�o���Ń}�U�����ɑ��̖�
�����ŁA�v�Ǝ��ʂ����ɑ��̖��W�F���[���}���t�����X�ɘA��Ă����B2�l�̖��ɃI���^���X�E�}
���V�j�����邪�A���̐l�̓C�M���X���`���[���Y2���̈����ɂȂ��Ă���B�]���̔��l�o����
���������B
�����ŁA�v�Ǝ��ʂ����ɑ��̖��W�F���[���}���t�����X�ɘA��Ă����B2�l�̖��ɃI���^���X�E�}
���V�j�����邪�A���̐l�̓C�M���X���`���[���Y2���̈����ɂȂ��Ă���B�]���̔��l�o����
���������B
�@�܂� Henrietta Anne Stuart�Ƃ��������́A�`���[���Y2���̖��ŁA���C14���̒�I�����A��
���ɉł��������B���̋`���Ƃ̊W�͂������ɋ{��ł���������ꂽ�E�E�E�B
���ɉł��������B���̋`���Ƃ̊W�͂������ɋ{��ł���������ꂽ�E�E�E�B
�@���āA�Ō�̈���(�ƌ����Ă����C�͂��������E�E�E)�A�ہA�����̏،��ɏ]���A�閧��������
�����j�̉A�̉��܂���}���g�m���v�l���A���̐�ΌN��̑㖼���̂��Ƃ����C14���ɓ�����
���A�������������j�I�ȑ厖���ɂ��Ă����ł͌�肽���B
�����j�̉A�̉��܂���}���g�m���v�l���A���̐�ΌN��̑㖼���̂��Ƃ����C14���ɓ�����
���A�������������j�I�ȑ厖���ɂ��Ă����ł͌�肽���B
�@�ޏ��͌h�i�ȃJ�g���b�N���k�ł���A����͋ɂ߂Č������@���I�ȏ�M���Ă����B������
�z��҂Ƃ��ĘV�N�̉��_�I�ɂ��x�z���������������B(���̊ȒP�Ȑ��U�́u���j�̒��̃V
���f���������v���Q�Ɗ肢����)
�z��҂Ƃ��ĘV�N�̉��_�I�ɂ��x�z���������������B(���̊ȒP�Ȑ��U�́u���j�̒��̃V
���f���������v���Q�Ɗ肢����)
 ��
��
�@�ޏ��̏@���I�M��́A�V�N�̍����̎�C�A�܂肱�̐��ł̍߂̐��X�ɋ��������n�߂�
�j�ɂƂ��āA�ӖړI�ɏ]���ׂ��L���X�g���k�Ƃ��Ă̖ƍߕ��ł���Ɗ������悤���B
�j�ɂƂ��āA�ӖړI�ɏ]���ׂ��L���X�g���k�Ƃ��Ă̖ƍߕ��ł���Ɗ������悤���B
�@�J�g���b�N�ɂ��@���̓���Ȃ����āA���Ƃ̓���͂Ȃ��A���̎��Ƃ𐬂������邱�Ƃɂ��A
�ނ̍߂��������B�E�E�B�܂�V���k�̎��R����C�����u�i���g�̌��߁v��p�~���邱�ƁA����
�̐V���k(���O�m�[)���������@������厖�Ƃ����A�ނɉۂ���ꂽ�g���ł���E�E�E�E�ƁB
�ނ̍߂��������B�E�E�B�܂�V���k�̎��R����C�����u�i���g�̌��߁v��p�~���邱�ƁA����
�̐V���k(���O�m�[)���������@������厖�Ƃ����A�ނɉۂ���ꂽ�g���ł���E�E�E�E�ƁB
�@����ȋ����ϔO���}���g�m���v�l�ɂ���ĉ萶�����̂ł���B1685�N10��18���A�������āu�i
���g���ߔp�~�v�̉��������z�����B(�t�H���e�[�k�u���[���߁B1787�N�Ƀ��F���T�C�����߂�
�p�~�����܂ő���)
���g���ߔp�~�v�̉��������z�����B(�t�H���e�[�k�u���[���߁B1787�N�Ƀ��F���T�C�����߂�
�p�~�����܂ő���)
�@����20���̐l�����A����M�������ʏ����Ɏ���܂ł̐l�X���A���̉����ɂ��t�����X��
�̂ĂāA���O�ɖS�����邱�ƂɂȂ�A�o�ϓI�����͌v��m��Ȃ��B�P���������C14���̌���
�ő�̉��_�����̂ł���B
�̂ĂāA���O�ɖS�����邱�ƂɂȂ�A�o�ϓI�����͌v��m��Ȃ��B�P���������C14���̌���
�ő�̉��_�����̂ł���B


�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���R���@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���Q�����V���k�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�@��l�̏����̔M���I�ȏ@���S���A20���̐l�X�̐l����ς����B���̌�A�ꐢ�I�ɓn���
50���l�̉^����ς����̂ł���B�l����20����1�̖S���҂��o���A�e�n�ŋ������@��C����
���闳�R���������h������A����⋭�����e�̗����Ȋ�����B
50���l�̉^����ς����̂ł���B�l����20����1�̖S���҂��o���A�e�n�ŋ������@��C����
���闳�R���������h������A����⋭�����e�̗����Ȋ�����B
�@�ߑ�̗��j�Ƃ����́A�}���g�m���v�l�ߔp�~�̒��{�l�Ƃ��Ĕ����B���C���������A
���̏����̎v�z�I�e���͂ɖӏ]���Ă��������߂ɁA�u���{�����Ƃ̗��j�Ɍ���I�ȉ��_��
�c�����킯���B
���̏����̎v�z�I�e���͂ɖӏ]���Ă��������߂ɁA�u���{�����Ƃ̗��j�Ɍ���I�ȉ��_��
�c�����킯���B
�@�������A���́u�i���g�̒��߁v�A���A�ǂ̂悤�ɐ��肳�ꂽ�̂�?
�@����́A1598�N4��13���A��̍D�F�ȉ��l�A�����S���ɂ���Ĕ��z���ꂽ�M�̎��R��錾
�������߂ł���B
�������߂ł���B
�@����ɂ��A�V���k�Ƌ����k�Ƃ̒��������������I�������킯���B
�@�����A������A�������ɑ����������҂��܂��A�J�u���G���E�f�X�g���Ƃ��������B
 �@�@
�@�@
�@������܂��������ߏ�ł������B�A�������͔ޏ��ɂ�������ł������̂ł��邪�A�ޏ���
�����̈������l���q�Z�U�[���ƁA�ǂ��ɂ��t�����X�[�̎��Y�Ƃł���V���k�M������
�N�[�����݂̈�l�������������悤�ƍl���Ă����B
�@����ɂ͏@�����ō����ƑΗ����Ă��郁���N�[�����݂Ƃ̌��I�Șa�����K�v�ł���A
�����ʼn��̈���ɑi���āA�����̐V�����h�̘a����ژ_�킯�ł���B
�@���̎������~�̂������ŁA�t�����X�͏@���I��������������A�����ɏI�~�����������B
�@���ꂪ�A�V���ɖ������u�i���g�̒��߁v�A�Ƃ����킯���B

�@�K�u���G���E�f�X�g���̔L�ȂŐ��́u�˂��A���肢�v�̈ꌾ���A�ꐢ�I�̌�A�}���g�m���v�l��
�u�˂��A�肢�v�̈ꌾ�ł��������āu�i���g�̒��ߔp�~�v�ƂȂ��������̂��Ƃł���B
�u�˂��A�肢�v�̈ꌾ�ł��������āu�i���g�̒��ߔp�~�v�ƂȂ��������̂��Ƃł���B
�u���j�͖������v�̍D�Ⴞ�B

�@�v���C�Z�������t���[�h���q2���́A1756�N�̂�����A����O����g��������炳�ꂽ����
��������B
��������B
�@8���̃I�[�X�g���A�R��15���̃��V�A�R���t�����X�R�̑������ăv���C�Z���ɑ��đ��U
�����J�n����A�Ƃ����̂��B
�����J�n����A�Ƃ����̂��B

�@�v���C�Z���͌R���卑�ł͂��������A�����\�̕��͂�11��6����x�ł���B��̃I�[�X�g
���A�p���푈�ʼnX���������̖��A�I�[�X�g���A����엀�ȃV�����W�G���n����D���āA�S����
�E����y�����Ƃ͌����A�l��400���̏������B�I�[�X�g���A�A���V�A�A�t�����X�̏��卑��G��
�ẮA�t�����X�̏h�G�C�M���X�𖡕��ɂ����ƂāA���͕K���A���W���錩�ʂ����B�����A
���N5��15���C�M���X�̃t�����X�ɑ�����z���ɂ���āA��[�͊J���ꂽ�B
���A�p���푈�ʼnX���������̖��A�I�[�X�g���A����엀�ȃV�����W�G���n����D���āA�S����
�E����y�����Ƃ͌����A�l��400���̏������B�I�[�X�g���A�A���V�A�A�t�����X�̏��卑��G��
�ẮA�t�����X�̏h�G�C�M���X�𖡕��ɂ����ƂāA���͕K���A���W���錩�ʂ����B�����A
���N5��15���C�M���X�̃t�����X�ɑ�����z���ɂ���āA��[�͊J���ꂽ�B
�@���ꂪ�A�S�����ɂ��炵�����N�푈�ł���A�I��܂łɂ͖�S�����̐l�����������
��푈�̎n�܂�Ȃ̂ł���B
��푈�̎n�܂�Ȃ̂ł���B
�@�����ŁA�v���C�Z�����t���[�h���q2�����������̂��ꂽ�̂́A�I�ɓn��p���𑱂�
�Ă����t�����X�ƃI�[�X�g���A�̗������A����A��������ƃ��F���T�C�����ɒ���A��������
���Ƃ������B
�Ă����t�����X�ƃI�[�X�g���A�̗������A����A��������ƃ��F���T�C�����ɒ���A��������
���Ƃ������B
�@��̐푈�ł���������Ă������̗������A�}�ɘA������Ȃ�Ė��ɂ��v��ʐ���s���A��
���ɐV�����̂ł���B
���ɐV�����̂ł���B




�@�m���ɁA�t�����X�E�I�[�X�g���A�����́A�������F���X�}��(�����̋t�])�Ƃ��đS�������Q����
�������ł���A�����p���ɂ����J�T�m���@���u�����ׂ��o�����v�Ƃ��̉�z�^�ɋL���Ă���B
�������ł���A�����p���ɂ����J�T�m���@���u�����ׂ��o�����v�Ƃ��̉�z�^�ɋL���Ă���B
�@�t���[�h���q2������̓������t�����X�̍���̓G�ɋV����̂������͂Ȃ��̂��B
�@�ނ͌R�l���ł��������t���[�h���q�E�E�B���w�����P���ɁA���y�⎍�̂����D�����㑧�q��
���Č����A���S����Ăĕ߂��ꂽ�Ƃ��ȂǁA�E�c���S�߂Ƃ��Ď��Y��鍐���ꂽ���Ƃ�����
���B�K���A�����̍����̒���ɂ���Ė��E�������킯�����A�R�l�C���̕��e�Ƃ͑��e��Ȃ�
�����N�������B
���Č����A���S����Ăĕ߂��ꂽ�Ƃ��ȂǁA�E�c���S�߂Ƃ��Ď��Y��鍐���ꂽ���Ƃ�����
���B�K���A�����̍����̒���ɂ���Ė��E�������킯�����A�R�l�C���̕��e�Ƃ͑��e��Ȃ�
�����N�������B
�@�������A�ނ́A���炪���ʂɂ���A���e�܂���̎�r���A�v���C�Z�������R�����Ƃ�
����������Ƃ����̋Ƃ𐬂�������B�����āA���e������N���푈���J�n�A�������͂邩
�ɑ�_�ȌR�l���ɂȂ����̂��B
����������Ƃ����̋Ƃ𐬂�������B�����āA���e������N���푈���J�n�A�������͂邩
�ɑ�_�ȌR�l���ɂȂ����̂��B
 �@�@�@�@�@�@�@�@
�@�@�@�@�@�@�@�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@Friedrich Wilhelm I�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�g���a�̊h���ҁh�t���[�h���q2���Ƃ��̃v���C�Z���R
�@�����āA���ł́A�u���a�̊h���ҁv�ȂǂƊe������Ă�Ă���n���B
�@����Ȓ��d�h�ȌN��ɕϖe�����t���[�h���q2���ɂƂ��āA�����⑤���Ƃ����V�ԑ����̍�
����X�J�[�g���͂��������ȂǁA���̂̑Ώۂł����Ȃ��B�Ƃ��낪�A����A�v���C�Z��������
�G�Ώ����̓��V�A�ɂ���A�I�[�X�g���A�ɂ��揗��̌N�Ղ���鍑�Ȃ̂ł���B���V�A��
�G���U���F�[�^����A�I�[�X�g���A�̓}���A�E�e���W�A���邾�B��҂̓V�����W�G���n���̑��D��
�ő剎�̒��A�t���[�h���q���ؐl�ƌĂсA���Ɨ��Q�̒��ڂ�����������U�̏h�G�ł���A��
�ɐ푈�̑���ł���B
����X�J�[�g���͂��������ȂǁA���̂̑Ώۂł����Ȃ��B�Ƃ��낪�A����A�v���C�Z��������
�G�Ώ����̓��V�A�ɂ���A�I�[�X�g���A�ɂ��揗��̌N�Ղ���鍑�Ȃ̂ł���B���V�A��
�G���U���F�[�^����A�I�[�X�g���A�̓}���A�E�e���W�A���邾�B��҂̓V�����W�G���n���̑��D��
�ő剎�̒��A�t���[�h���q���ؐl�ƌĂсA���Ɨ��Q�̒��ڂ�����������U�̏h�G�ł���A��
�ɐ푈�̑���ł���B
�@���������V�A�́A�v���C�Z���ɂƂ��āA���̃V�����W�G���n���ł̃I�[�X�g���A�Ƃْ̋���Ԃ�
��������A�G�ɉ����Ȃ��w��̋����B�O���̌���������Ă��F�D�W��ێ����Ă����˂�
�Ȃ�ʑ��肾�����B
��������A�G�ɉ����Ȃ��w��̋����B�O���̌���������Ă��F�D�W��ێ����Ă����˂�
�Ȃ�ʑ��肾�����B
�@�ʂĂ̒m��ʍL��ȃ��V�A�鍑�́u�퓬�ɏ��ĂĂ��푈�ɂ͏��ĂȂ��G�v�Ȃ̂ł���B
�@�Ƃ��낪�A���̃��V�A���A�O���������G�ɉ�����E�E�E�B
�@����́A���V�A�����v���C�Z���̗̗L��_���Ă������ʂ����邪�A����Ȃ��Ƃ����A����G
���U���F�[�^�̃t���[�h���q�ɑ���u�����݁v�����̍���ɂ������̂��B
���U���F�[�^�̃t���[�h���q�ɑ���u�����݁v�����̍���ɂ������̂��B

�@�t���[�h���q�́A�����́A�����ɑ���݂̂���A�����n���ȏ��S���������肵�Ă���
���A���V�A�鍑�ɑ��鋰�|�S����̃X�g���X�����ɁA��������l���҂����Ԃ݂̑����
���Ă���������A�Q�Ԓ��ŕ�������Ă��肢�邭���ɁA1��5�璅���̃h���X�������Ă���̂�
�s�v�c�A�Ƃ��R�P�ɂ��邾���R�P�ɂ��Ă����B
���A���V�A�鍑�ɑ��鋰�|�S����̃X�g���X�����ɁA��������l���҂����Ԃ݂̑����
���Ă���������A�Q�Ԓ��ŕ�������Ă��肢�邭���ɁA1��5�璅���̃h���X�������Ă���̂�
�s�v�c�A�Ƃ��R�P�ɂ��邾���R�P�ɂ��Ă����B
�@����ȉA����`������������́A���Ƃ��Ă��̃v���C�Z���̕����j��[���������A15����
���͂ň�A�ӂ����Ă�낤�Ƌ@���T���Ă����̂ł���B
���͂ň�A�ӂ����Ă�낤�Ƌ@���T���Ă����̂ł���B
�@��ЂƂ́A�܂��ɂ��̂��Ƃ��B
 �@
�@
�@�t���[�h���q2���́A�u�O�叩�w�v�Ƃ��u�y�`�R�[�g�P���É��A�Q���É��A�R���É��v�Ƃ��̖\����
�D��œf���Ă����B�O�叩�w�̈�l�ځA��l�ڂ́A�����܂ł��Ȃ��A�I�[�X�g���A����}���A�E�e
���W�A�ƃ��V�A����G���U���F�[�^�A�y�`�R�[�g�P���É��ƂQ���É����A���R�̂��ƁA���̓�l��
�����ł���B
�D��œf���Ă����B�O�叩�w�̈�l�ځA��l�ڂ́A�����܂ł��Ȃ��A�I�[�X�g���A����}���A�E�e
���W�A�ƃ��V�A����G���U���F�[�^�A�y�`�R�[�g�P���É��ƂQ���É����A���R�̂��ƁA���̓�l��
�����ł���B
�@�ł́A�O�l�ځA�܂�O�叩�w�̎O�l�ڂł���y�`�R�[�g�R���É��Ƃ́A�N�𑄋ʂɂ�����
�����̂�?
�����̂�?
�@���ꂱ���A���̎��N�푈�ɍۂ��āA�S���[���b�p�����������A�t���[�h���q�剤�����n�Ɋׂ�
���u�����̋t�]�v�������炵���ꏗ���Ȃ̂ł���B
���u�����̋t�]�v�������炵���ꏗ���Ȃ̂ł���B
�@�@�@�@���V�A����G���U���F�[�^

�@ �@
�@ �@
�@
 �@
�@ �@
�@
�@�@�@�I�[�X�g���A����}���A�E�e���W�A�@�@�@�@�t���[�h���q�@�@�@�@�@�|���p�h�D�[����ݕv�l
�@�|���p�h�D�[����ݕv�l�A�ޏ������̎O�l�ځA�Ȃ̂��B
�@�ޏ��͒��Ƃ̏o�����A���̔��e�Ƌ��{�ɂ���ăt�����X�������C�P�T���̑����A�܂����
�����ƂȂ����B���������̒n�ʂ́A��b��O���̑�g�炩�����ڒu����A�{���������A
�����ɂ��֗^�ł�����Ȍ��͂������ł���B
�����ƂȂ����B���������̒n�ʂ́A��b��O���̑�g�炩�����ڒu����A�{���������A
�����ɂ��֗^�ł�����Ȍ��͂������ł���B

�@���C�P�T���̓��C�E���E�r�����E�G�[��(���Ă��ĉ�)�Ɛl�X�ɌĂꂽ�F�j�A�I�������̈�����
�����Ă����l���B�u���̉��v�ƌĂꂽ�閧�قɂ͏��������͂��A���X�Ɖ��̂�����ɋ���
��ꂽ�B����ȍD�F�ȍ����ł��������A�|���p�h�D�[���v�l�́A���̒j�Ƃ��Ă̗~�]�̔��I��
�͖ڂ��ނ�A�����͗ǂ��F�A�����ҁA�l�X�Ȍ�y�̒҂Ƃ��Ă̗����ێ����A���ʂ܂�
�����Ƃ̓��ʂȊW����蔲���������ł������B
�����Ă����l���B�u���̉��v�ƌĂꂽ�閧�قɂ͏��������͂��A���X�Ɖ��̂�����ɋ���
��ꂽ�B����ȍD�F�ȍ����ł��������A�|���p�h�D�[���v�l�́A���̒j�Ƃ��Ă̗~�]�̔��I��
�͖ڂ��ނ�A�����͗ǂ��F�A�����ҁA�l�X�Ȍ�y�̒҂Ƃ��Ă̗����ێ����A���ʂ܂�
�����Ƃ̓��ʂȊW����蔲���������ł������B
�@��b��Ǖ�������A���R��C��������A�ޏ��́A�����ɂ͂��܂�S�̂Ȃ������ɐ�����
��������d�������B
��������d�������B
�@�������A�ޏ��́A���������邩�m��ʑ����̐g�A���������邽���Ƃ͈Ⴄ�B���܂�����F
�͒��ƁA����M���ł͂Ȃ��B����ȁA�ʂ�������Ȃ��n���f�B�[������B
�͒��ƁA����M���ł͂Ȃ��B����ȁA�ʂ�������Ȃ��n���f�B�[������B
�@���������܂����p�����̂��I�[�X�g���A����̃}���A�E�e���W�A�������B
�@�ޏ��̔h������������g�J�E�j�b�c���݂́A����ɁA�܂�ʼn����ɐڂ���悤�Ƀ|���p�h�D
�[���v�l�ɉ�����B�����ď���́A�ޏ����u�e�F�v�ƌĂсA�����ɓn���ėF����X�����B
�[���v�l�ɉ�����B�����ď���́A�ޏ����u�e�F�v�ƌĂсA�����ɓn���ėF����X�����B
�@�@�@�@�@�@�@ �@
�@
 �@
�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@Madame de Pompadour�@�@�@�@�@�@Graf von Kaunitz-Rietberg
�@����ɂ̓|���p�h�D�[���v�l���L���V�ɂȂ����B
�@����Ɉ��������A�v���C�Z���̃t���[�h���q2���́A�����̏����̎�����A�O����̗F�D����
����t�����X�̌��������ɑ��āA�U�X�̈������������A�����̎������Ƀ|���p�h�D�[���Ɩ�
�t���R����A��M����悤�Ȏ�������Ă͉x�ɓ����Ă���炵���B
����t�����X�̌��������ɑ��āA�U�X�̈������������A�����̎������Ƀ|���p�h�D�[���Ɩ�
�t���R����A��M����悤�Ȏ�������Ă͉x�ɓ����Ă���炵���B
�@��l�Ƃ��āA����Ȋ����p�̓������ɁA�������u�e�F�v�ƌĂԃ}���A�E�e���W�A����ƓG��
���A�������u���w�v�ƌĂԃt���[�h���q�剤�Ɠ��������ԂȂǂƂ����|���͕s�\���낤�B
���A�������u���w�v�ƌĂԃt���[�h���q�剤�Ɠ��������ԂȂǂƂ����|���͕s�\���낤�B
�@�ޏ��́A���ς�炸�e�v���C�Z���A���I�[�X�g���A�h�̑����t�����X�{��̏��h��}���āA��
���A�n�m�[���@�[�ł̑C�M���X�̓����ɂ����ăv���C�Z���Ƃ̓������K�v�ł���Ƃ������Ɨ�
���ɔ����āA�I�[�X�g���A�Ƃ̓�����O��咣���A�������C15�����́u�˂��A���肢�v�Ő���
�����A���F���T�C�����̒����ƂȂ����̂ł���B�����ă��[���b�p�����̐��͋ϐ��͕���A
�Ăѐ헐�A21���̃t�����X�R�����A �h�C�c�̐���i�����Ă������̂ł������B(�]�k3)
���A�n�m�[���@�[�ł̑C�M���X�̓����ɂ����ăv���C�Z���Ƃ̓������K�v�ł���Ƃ������Ɨ�
���ɔ����āA�I�[�X�g���A�Ƃ̓�����O��咣���A�������C15�����́u�˂��A���肢�v�Ő���
�����A���F���T�C�����̒����ƂȂ����̂ł���B�����ă��[���b�p�����̐��͋ϐ��͕���A
�Ăѐ헐�A21���̃t�����X�R�����A �h�C�c�̐���i�����Ă������̂ł������B(�]�k3)

�@���N�푈�A�����̗��j�Ƃ����̌������Ƃ����푈�́A�����̂��Ƃ��n�܂����̂ł���B
�E�E�E���̐푈�ɂ��A�t�����X�̓J�i�_�ƃC���h�̔����̐A���n���C�M���X�ɒD���A���ȍ�
�ƓI�������邱�ƂɂȂ�̂ł���B
�ƓI�������邱�ƂɂȂ�̂ł���B
�@��������A�����݂�����B�ǂ��������������̍��܂�ł���A�N���I�p�g���̕@�ł͂Ȃ�
���A�l�ނ̗��j�̗��ꂪ�����������ׂȖ��(���l�����ɂ͑��肾��)�ɂ���Č������Ƃ���
��ς��Ă��܂��̂ł���B
���A�l�ނ̗��j�̗��ꂪ�����������ׂȖ��(���l�����ɂ͑��肾��)�ɂ���Č������Ƃ���
��ς��Ă��܂��̂ł���B
�@�܂������A���������j���̓���Ș_�q��ǂނ̂��n���炵���Ȃ�悤�ȋA���ł��邪�A����
�ȕ��ȗv�����͂̕������͂͂��邵�A�����ʔ����B
�ȕ��ȗv�����͂̕������͂͂��邵�A�����ʔ����B
�@�w�ʂ��擾������A���j�w���Ŗ��𐬂����ȂǂƖ�N�ɂȂ�ƁA�ߑ㍑�Ɛ����ߒ��ɉ�����
�]�X�Ƃ������@���v�z�����̕\�ʉ��Ƃ��嗤�푈�ƐA���n���D�̐��E�j�I�Ӌ`�Ƃ��A
�_�|�͊w�p�p��Ɋ��S�������ꂽ�����̏W�听�����W����ے�ƍm����J��Ԃ��A�Ñ�
����ߑ�܂ł���{�̐��R������j�I�^���Ƃ��ő��˂悤�Ƃ���B������܂���ςȓ��
�ł��邪�A�߂��������o�����̏W�ςɉ������߂Ă������肾�B
�]�X�Ƃ������@���v�z�����̕\�ʉ��Ƃ��嗤�푈�ƐA���n���D�̐��E�j�I�Ӌ`�Ƃ��A
�_�|�͊w�p�p��Ɋ��S�������ꂽ�����̏W�听�����W����ے�ƍm����J��Ԃ��A�Ñ�
����ߑ�܂ł���{�̐��R������j�I�^���Ƃ��ő��˂悤�Ƃ���B������܂���ςȓ��
�ł��邪�A�߂��������o�����̏W�ςɉ������߂Ă������肾�B
�@���߂Đ������l�Ԃ̍��̕��ՓI�Ȑ������A���邢�͋��������y�������ł͂Ȃ����B�ނ��낻
���Ɉ�{�̐��R����^���������邩���m��Ȃ��B
���Ɉ�{�̐��R����^���������邩���m��Ȃ��B
�����]�k�R�[�i�[
(�]�k1)
�@�̂��K���X�ŏo���Ă���Ǝv���Ă������V�������[�ɑ��̖��Ƃ����̂́A Nicole du Plessis-
Richelieu (1587-1635)�B1617�N�Ƀu���[��݃E���o���E�h�E�}�C�G�ƌ������Ă���̂Ńu���[��
�ݕv�l�B�v�͏���u���[��݂ŁA�X�E�F�[�f����g(1631)�����߂��R�l�Ńt�����X�����ƂȂ�
��(1632)�B���̈�b�́A�^���}���E�f�E���I�\�ɂ��B�u�ޏ��͎������K���X�̂��K�������Ă���
�Ǝv���Ă���A���肽���Ȃ��Ǝv�����B �ޏ��͂������ȋ��C�̎��Ԃ��߂������B���S�ɐ��C�ł�
�Ȃ��v�Əq�ׂ��Ă���B
Richelieu (1587-1635)�B1617�N�Ƀu���[��݃E���o���E�h�E�}�C�G�ƌ������Ă���̂Ńu���[��
�ݕv�l�B�v�͏���u���[��݂ŁA�X�E�F�[�f����g(1631)�����߂��R�l�Ńt�����X�����ƂȂ�
��(1632)�B���̈�b�́A�^���}���E�f�E���I�\�ɂ��B�u�ޏ��͎������K���X�̂��K�������Ă���
�Ǝv���Ă���A���肽���Ȃ��Ǝv�����B �ޏ��͂������ȋ��C�̎��Ԃ��߂������B���S�ɐ��C�ł�
�Ȃ��v�Əq�ׂ��Ă���B
 �@Urbain de Maille, marquis de Breze (1598-1650)
�@Urbain de Maille, marquis de Breze (1598-1650)(�]�k2)
�@���̌�����1652�N7��30���A�p���̃v�`�E�y�[���L��ł��ꂼ��4���̉�Y�l���܂߂čs��
�ꂽ�B���Ƃ��Ƃ͔��R�̍���c�̐ȏ�A�ӌ��̑Η�����{�[�t�H�[�������`��̃k���[��
��(�k���[�����v�l�̓{�[�t�H�[���̎o�G���U�x�X�E�h�E�u���{�������A�N��̓{�[�t�H�[����
�����k���[�������8�Ώ�)�Ɏ���グ�����Ƃ����������B����ȑΗ��̔w�i�ɂ́A���e�̃V��
�e�B�������v�l�ւ̓�l�̎v�����炭��G���S���������킯���B(���v�l�̕v�V���e�B��������3
�N�O�ɃV�������g���̐�ʼn��R�̏��Ƃ���28�Ő펀���Ă��邩�珮�X��)
�ꂽ�B���Ƃ��Ƃ͔��R�̍���c�̐ȏ�A�ӌ��̑Η�����{�[�t�H�[�������`��̃k���[��
��(�k���[�����v�l�̓{�[�t�H�[���̎o�G���U�x�X�E�h�E�u���{�������A�N��̓{�[�t�H�[����
�����k���[�������8�Ώ�)�Ɏ���グ�����Ƃ����������B����ȑΗ��̔w�i�ɂ́A���e�̃V��
�e�B�������v�l�ւ̓�l�̎v�����炭��G���S���������킯���B(���v�l�̕v�V���e�B��������3
�N�O�ɃV�������g���̐�ʼn��R�̏��Ƃ���28�Ő펀���Ă��邩�珮�X��)
 �@�@�@�@
�@�@�@�@ �@�@�@�@
�@�@�@�@
�@Duc de Nemours�@�@�@�@�@Elisabeth de Bourbon-Vendome �@�@Duc de Beaufort
�@���������Ƃ͌����A�������N�����Ă���Œ����A�{�[�t�H�[�����͓{���Č����ɋy�ڂ��Ƃ���
�`��ɑ��āA�Ӎ߂��āA���x���a����\�����ꂽ���A���ǂ͌�����������Ȃ������B
�`��ɑ��āA�Ӎ߂��āA���x���a����\�����ꂽ���A���ǂ͌�����������Ȃ������B
�@�����̏�ɉ����Ă��A�{�[�t�H�[���́u�ߋ��͖Y��āA�܂��ǂ��F�ɂȂ낤�v�ƍŌ�̎Ӎ߂�
�\��������������A�k���[���́u�ق�A���i��Y�B���͂�E�����E����邩���v�Ǝ��ꂸ�A
��ɒZ�e�����B���ꂪ������ʂƌ����A������ɋ`�Z�ɓ˂����������B��ނȂ��{�[�t
�H�[�����������e�e�Ńk���[���͑�������B
�\��������������A�k���[���́u�ق�A���i��Y�B���͂�E�����E����邩���v�Ǝ��ꂸ�A
��ɒZ�e�����B���ꂪ������ʂƌ����A������ɋ`�Z�ɓ˂����������B��ނȂ��{�[�t
�H�[�����������e�e�Ńk���[���͑�������B
�@������4�l�̉�Y�l���m�����������A�k���[�����̃��B���[����(Villars)���{�[�t�H�[������
�e�q�������̃G���N�[��(Hericourt)��|���A��͂�k���[�����̃����[���V��(�܂��̓f���[��
�V��Luzerche)������̃��[(de Ris)��|���B�|���ꂽ��l�͂��̓��̓��Ɏ��B�k���[����
�̃��E�V�F�[�Y�m��(la Chaise)�A�J���p��(Campan)�������A�{�[�t�H�[�����̃r�����[����
(comte de Bury)���u���G(Brillet)�����ɕ������A���݂͏d���������B�S�̓I�ɂ̓k���[������
���������A�̐S�ȓ��l������������d���Ȃ��B
�e�q�������̃G���N�[��(Hericourt)��|���A��͂�k���[�����̃����[���V��(�܂��̓f���[��
�V��Luzerche)������̃��[(de Ris)��|���B�|���ꂽ��l�͂��̓��̓��Ɏ��B�k���[����
�̃��E�V�F�[�Y�m��(la Chaise)�A�J���p��(Campan)�������A�{�[�t�H�[�����̃r�����[����
(comte de Bury)���u���G(Brillet)�����ɕ������A���݂͏d���������B�S�̓I�ɂ̓k���[������
���������A�̐S�ȓ��l������������d���Ȃ��B
�@���̂悤�ȉ�Y�l���܂�ł̓����Ƃ����`���́A���C13���A14������t�����X�ł͈�ʓI��
�����B���Ƃ��Ɖ�Y�l���x�Ƃ́A�������铖���҂����̎������A�����ɍs���邩���m�F����
���߂̏ؐl�������̂����A�������A�o���̏ؐl���m�����Ԃɋ`�����Ă��ē����Ƃ������Ƃ�
�K�����������̂ł���B
�����B���Ƃ��Ɖ�Y�l���x�Ƃ́A�������铖���҂����̎������A�����ɍs���邩���m�F����
���߂̏ؐl�������̂����A�������A�o���̏ؐl���m�����Ԃɋ`�����Ă��ē����Ƃ������Ƃ�
�K�����������̂ł���B
�@ �@
�@
 �@
�@
Francoisde Montmorency-Bouteville�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����C�����L��̌���
�@�V���e�B�������v�l���`�Z������������ɋy����ȂǍߍ��Ȍ�w�l�ł��邪�A��������
���̐l�̕��e�͗L���ȃt�����\���E�h�E�����������V�\�E�u�[�g���B��Francoisde Montmorency-
Bouteville(1600-27)���B�f���G���X�g�A�܂茈�����Ŗ��̒m�ꂽ�L���l�B����M���̏o�Ȃ�
�ɁA���ׂȂ��Ƃł����Ɍ��������A�֎~�߂��ɌY��݂��Ă��ǂ����������B1624�N�|���W�{�[��
��Comte de Pontgibaud�������ŎE�Q�A��25�N�ɂ��h�E���@�����Z�[De Valencay�Ƃ���������
�́A�|���g���Marquis de Portes���E���́B�����ė�26�N�g���j�\����Comte de Thorigny��
�E���āA������Ƀ��E�t���b�g�j��Baron de La Frette�������A���V�������[�ɑ��̋t�ɐG��
��(���R����)�A���O�ɓ��S�B
���̐l�̕��e�͗L���ȃt�����\���E�h�E�����������V�\�E�u�[�g���B��Francoisde Montmorency-
Bouteville(1600-27)���B�f���G���X�g�A�܂茈�����Ŗ��̒m�ꂽ�L���l�B����M���̏o�Ȃ�
�ɁA���ׂȂ��Ƃł����Ɍ��������A�֎~�߂��ɌY��݂��Ă��ǂ����������B1624�N�|���W�{�[��
��Comte de Pontgibaud�������ŎE�Q�A��25�N�ɂ��h�E���@�����Z�[De Valencay�Ƃ���������
�́A�|���g���Marquis de Portes���E���́B�����ė�26�N�g���j�\����Comte de Thorigny��
�E���āA������Ƀ��E�t���b�g�j��Baron de La Frette�������A���V�������[�ɑ��̋t�ɐG��
��(���R����)�A���O�ɓ��S�B
�@�������A�g���j�\���̐e���̃u�\����������Comte de Beuvron���猈���͂��A���x��
�f�����B����ŁA�������ɑ����A�������������A�u�\�������ɍēx���킳�ꂽ�炠������Ɖ���
�āA�p���̂ǐ^�A�����C�����L��Ń����������V�\�E�u�[�g���B���͐e�ʂ̃V���y������
Comte des Chapelles����Y�l�ɁA�u�\���������݂̓r���V�[�E�_���{���[�Y���Marquis de
Bussy d'Amboise����Y�l�Ƃ��đ嗧���B�u�[�g���B�����r���V�[�E�_���{���[�Y��|���E��
�ƁA�����ɂ݂�Ȉ����グ���B�����������Ă��邩��ŁA�u�\���������̓C�M���X�ɓ��S����B
�������A�u�[�g���B���ƃV���y���́A���x�����͂ƕ߂���ꂽ�B
�f�����B����ŁA�������ɑ����A�������������A�u�\�������ɍēx���킳�ꂽ�炠������Ɖ���
�āA�p���̂ǐ^�A�����C�����L��Ń����������V�\�E�u�[�g���B���͐e�ʂ̃V���y������
Comte des Chapelles����Y�l�ɁA�u�\���������݂̓r���V�[�E�_���{���[�Y���Marquis de
Bussy d'Amboise����Y�l�Ƃ��đ嗧���B�u�[�g���B�����r���V�[�E�_���{���[�Y��|���E��
�ƁA�����ɂ݂�Ȉ����グ���B�����������Ă��邩��ŁA�u�\���������̓C�M���X�ɓ��S����B
�������A�u�[�g���B���ƃV���y���́A���x�����͂ƕ߂���ꂽ�B
 �@�����̍�������A�s�����B
�@�����̍�������A�s�����B�@���̌����֎~�߂����n���ɂ��Ė��������������������A���ɖ���M��������Ƃ̉�����
��̉���������ꂸ�A�����̍����ւ̒��i�����A�V���y�������X�A�O���[���L��Ŏa���
�Ȃ����B
��̉���������ꂸ�A�����̍����ւ̒��i�����A�V���y�������X�A�O���[���L��Ŏa���
�Ȃ����B
�@�u�[�g���B���̐��܂������Z���l�����������ďI������킯�����A�ނ͓�j���₵�A����
��l�͏�q�̂��������ȃV���e�B�������v�l�����A���̒�̃t�����\���E�A�����͌�Ƀ����N�T
���u�[�������Ƃ��ă��C14���̐N���푈�ő傢�Ɋ���p�Y�ƂȂ�l�����B�܂��A������
�q����������������������G���U�x�X�E�A���W�F���N���A��̉�̂悤�ɕv�̏����͊���Ȃ�
�������A91�N���̒�����S�����Ă���B
��l�͏�q�̂��������ȃV���e�B�������v�l�����A���̒�̃t�����\���E�A�����͌�Ƀ����N�T
���u�[�������Ƃ��ă��C14���̐N���푈�ő傢�Ɋ���p�Y�ƂȂ�l�����B�܂��A������
�q����������������������G���U�x�X�E�A���W�F���N���A��̉�̂悤�ɕv�̏����͊���Ȃ�
�������A91�N���̒�����S�����Ă���B
�@�@ �@
�@ �@
�@
 �@
�@ �@
�@
�@Henri II de Lorraine, Duc de Guise �@�@�@Godefroi, Comte d'Estrades �@�@�@�@�@�@Bridieu, Louis de
�@������A�t�������Ă����ƁA��̃V���e�B�������v�l�̕v�̌Z���[���X�E�h�E�R���j�[���݂��A
�����O���B�����ݕv�l�̖��_�̂��߂ɁA�M�[�Y���݂Ɍ�����\������ŁA������܂������C��
���L��ŁA�R���j�[����Y�l�f�X�g���[�h����Comte d'Estrades�A�M�[�Y����Y�l�u���f���[
���Marquis de Bridieu�A�����Ă�4�l�œ��X�ƌ����A�M�[�Y���ɐ[��킳��A���Â�����
���������Ɏ���ł���B(1644�N)
�����O���B�����ݕv�l�̖��_�̂��߂ɁA�M�[�Y���݂Ɍ�����\������ŁA������܂������C��
���L��ŁA�R���j�[����Y�l�f�X�g���[�h����Comte d'Estrades�A�M�[�Y����Y�l�u���f���[
���Marquis de Bridieu�A�����Ă�4�l�œ��X�ƌ����A�M�[�Y���ɐ[��킳��A���Â�����
���������Ɏ���ł���B(1644�N)
 �@
�@
Marquis de Sevigne�@ �@�@�@Marquise de Sevigne,Marie de Rabutin-Chantal
�@���Ȃ݂ɁA�{�[�t�H�[���ƃk���[���̌����̂������N�̑O�N1651�N�A���̗L���ȃZ���B�j�G
���ȏW�̃Z���B�j�G��ݕv�l�̕v�A�����E�h�E�Z���B�j�G(Henri de Sevigne)���S���h�����v�l��
�������l������g���u������_���u���m��(Francois Amanieu,chevalier d'Albret)�ƌ������āA��
�����͗ǂ����A�[���2����ɁA25�̎�Ȃ��₵�Ď���ł���B�ނ��܂��t�����h�̗���
���R�ɑg���Ă����B�_���u���m�݂͗L���ȃ_���u�������̒킾���A�Z�̂悤�ɖ����グ�邱��
���Ȃ��A1672�N�A�T���E���W�F�E�R���{������(comte de Saint-Leger-Corbon)�Ƃ̌����Ŗ���
�Ƃ��Ă���B���łɁA6�N��ɂ̓_���u���m�݂̑����҂ł��鉙�̃_���u����݂��A�����b�g
����(Comte de Lameth)�̉����Ɗ��ʂ��A�v�Ɍ����E����Ă���B���̌�݂��q���Ȃ��A�R��
����̒n�͍Ȃ̍č���֗���Ă��܂��A�_���u���Ƃ͌����ő呹���B
���ȏW�̃Z���B�j�G��ݕv�l�̕v�A�����E�h�E�Z���B�j�G(Henri de Sevigne)���S���h�����v�l��
�������l������g���u������_���u���m��(Francois Amanieu,chevalier d'Albret)�ƌ������āA��
�����͗ǂ����A�[���2����ɁA25�̎�Ȃ��₵�Ď���ł���B�ނ��܂��t�����h�̗���
���R�ɑg���Ă����B�_���u���m�݂͗L���ȃ_���u�������̒킾���A�Z�̂悤�ɖ����グ�邱��
���Ȃ��A1672�N�A�T���E���W�F�E�R���{������(comte de Saint-Leger-Corbon)�Ƃ̌����Ŗ���
�Ƃ��Ă���B���łɁA6�N��ɂ̓_���u���m�݂̑����҂ł��鉙�̃_���u����݂��A�����b�g
����(Comte de Lameth)�̉����Ɗ��ʂ��A�v�Ɍ����E����Ă���B���̌�݂��q���Ȃ��A�R��
����̒n�͍Ȃ̍č���֗���Ă��܂��A�_���u���Ƃ͌����ő呹���B
�@�b�͖߂�A�v�Z���B�j�G��݂����l�̂��߂Ɍ������Ď��ɁA�₳�ꂽ��Ȃ����������A��
�̃Z���B�j�G��v�l�̕��e�����āA����������q�̌����������������V�[�E�u�[�g���B���̗F�l
�Ȃ̂��B�v�l�̕��̓V�����^���j��Baron de Chantal�Ƃ������A1624�N�Ƀu�[�g���B�����|���W
�{�[���݂��E���������ł́A�u�[�g���B�����̉�Y�l�Ƃ��ĎQ�����Ă��邭�炢�B�܂�A����
��D���M���̈�l�Ȃ̂��B
�̃Z���B�j�G��v�l�̕��e�����āA����������q�̌����������������V�[�E�u�[�g���B���̗F�l
�Ȃ̂��B�v�l�̕��̓V�����^���j��Baron de Chantal�Ƃ������A1624�N�Ƀu�[�g���B�����|���W
�{�[���݂��E���������ł́A�u�[�g���B�����̉�Y�l�Ƃ��ĎQ�����Ă��邭�炢�B�܂�A����
��D���M���̈�l�Ȃ̂��B

 ��1768�N��
��1768�N��
�Z���B�j�G�v�l�̕��V�����^���j�݁@�j�݂̕�Jeanne de Chantal�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@Sainte Jeanne de Chantal
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�v�Ǝ��ʌ�A�C�����ƂȂ�1610�N�C����u����K���v�n���B1641�N�v�B
�@���̓��A�����ՂŃV�����^���j�݂͉Ƒ��Ƌ���ŋF�������Ă����B����K���n���҂�
�h�i�ȃN���X�`�����ł���u���W�����k�E�h�E�V�����^���v�̑��q�Ȃ̂����瓖�R���낤�B�Ƃ��낪�A
�u�[�g���B���̌Ăяo���ɂ������܋�����яo���A�T���E�^���g���[�k��ɋ삯���āA�|���W
�{�[���Ƃ̓����ɎQ�������Ƃ����B�����ՂɌ��������Ƃ������Ƃō����@�@���i�����A�u��
�ʔ��D�A�M���g���͑r���ōi��Y�A��͔j��A���Y�͖v���A�Δ�ɍߏ����������̐Ւn
�Ɍ��Ă�v�ƌ������������B��e�͋������낤�B�������A�u�[�g���B�����j�݂����łɍ���т���
�������A�������e�����s����Ȃ������B�܂��u�[�g���B�����a��Y�̒��ڂ̌����ƂȂ��������C
�����L��ł̃u�\�������Ƃ̌����������N����������A�ނ̓V�����^���j�ݑ�ɂ܂��͓���
����Őg����߂Ă����A�Ƃ������炢�̒��ǂ����B�����̑��q��������D���Ƃ͂Ȃ�Ƃ��E�E�E
�h�i�ȃN���X�`�����ł���u���W�����k�E�h�E�V�����^���v�̑��q�Ȃ̂����瓖�R���낤�B�Ƃ��낪�A
�u�[�g���B���̌Ăяo���ɂ������܋�����яo���A�T���E�^���g���[�k��ɋ삯���āA�|���W
�{�[���Ƃ̓����ɎQ�������Ƃ����B�����ՂɌ��������Ƃ������Ƃō����@�@���i�����A�u��
�ʔ��D�A�M���g���͑r���ōi��Y�A��͔j��A���Y�͖v���A�Δ�ɍߏ����������̐Ւn
�Ɍ��Ă�v�ƌ������������B��e�͋������낤�B�������A�u�[�g���B�����j�݂����łɍ���т���
�������A�������e�����s����Ȃ������B�܂��u�[�g���B�����a��Y�̒��ڂ̌����ƂȂ��������C
�����L��ł̃u�\�������Ƃ̌����������N����������A�ނ̓V�����^���j�ݑ�ɂ܂��͓���
����Őg����߂Ă����A�Ƃ������炢�̒��ǂ����B�����̑��q��������D���Ƃ͂Ȃ�Ƃ��E�E�E
 �@
�@
Roger de Rabutin, comte de Bussy�@�@Marquise de Monglat,Cecile-Elisabeth Hurault de Cheverny
�@�����Č����A�Z���B�j�G��v�l���A���N�e��������ł����]�Z(�c�����m���Z��̖��]�Z
�����A�v�l�̏]�o�ƌ������ď]�Z�ɂȂ��Ă���)���W�F�E�h�E�r���V�[�E�h�E���s���^�����݂Ȃǂ��A
1638�N�Ƀh�E�r���X�Nde Busc�ƌ����ɂȂ�A����ɏd���킹�Ă���B(���N��ɑ���͎�
�S)�B���N���V�������v�l dame de Chalons �Ƃ̗����ŕʂ̌��������Ă���B���̂܂����N��
�̓u�b�Z���ݕv�lComtesse de Busset�Ɨ����ɂȂ�̂����E�E�E�B(�ނ��푈������⌈���Ȃ�
�̐l���̑��ɁA���l�̃����O����ݕv�lMarquise de Monglat�ׂ̈ɏ������u�S�[���̗��l��
���v�Ƃ����{��X�L�����_���W�݂����ȏ��������c���������o�X�e�B�[���ɓ������ꂽ��A�g��
����̐l���𑗂������Ƃ͏Ȃ�)
�����A�v�l�̏]�o�ƌ������ď]�Z�ɂȂ��Ă���)���W�F�E�h�E�r���V�[�E�h�E���s���^�����݂Ȃǂ��A
1638�N�Ƀh�E�r���X�Nde Busc�ƌ����ɂȂ�A����ɏd���킹�Ă���B(���N��ɑ���͎�
�S)�B���N���V�������v�l dame de Chalons �Ƃ̗����ŕʂ̌��������Ă���B���̂܂����N��
�̓u�b�Z���ݕv�lComtesse de Busset�Ɨ����ɂȂ�̂����E�E�E�B(�ނ��푈������⌈���Ȃ�
�̐l���̑��ɁA���l�̃����O����ݕv�lMarquise de Monglat�ׂ̈ɏ������u�S�[���̗��l��
���v�Ƃ����{��X�L�����_���W�݂����ȏ��������c���������o�X�e�B�[���ɓ������ꂽ��A�g��
����̐l���𑗂������Ƃ͏Ȃ�)
�@�����ЂƂ�����A�`���̃k���[���ƃ{�[�t�H�[����1652�N�̌����Ńk���[������Y�l��
���Č����ɎQ���A�{�[�t�H�[�����̐e�q�������̃G���N�[�����E�������B���[����̉��l
(Marie Gigault de Bellefonds�A�����͌����̑O�N��51�N)�́A�Z���B�j�G�v�l�̕��ʒ��Ԃł�
����B
���Č����ɎQ���A�{�[�t�H�[�����̐e�q�������̃G���N�[�����E�������B���[����̉��l
(Marie Gigault de Bellefonds�A�����͌����̑O�N��51�N)�́A�Z���B�j�G�v�l�̕��ʒ��Ԃł�
����B
������Ɗ֘A�����l������������肵�ďE���グ�Ă��A�M�������͐���ɖ��_���́A������
�ׂ̈Ɍ����ɋy��ł��邱�Ƃ�������B�����@�@�͖ܘ_�A�����@��Ȃǐꑮ�̋@�ւŗl�X��
�@�߂z���A���Ȃ茵�������Y���܂ʌY�����Ă��邪�A���ʂ̂قǂ͔����Ȃ��̂�
�����B�펞�łȂ��Ƃ��������m�Ŗ����U�炵�Ă������A���b�̂Ȃ��b�ł���B
�ׂ̈Ɍ����ɋy��ł��邱�Ƃ�������B�����@�@�͖ܘ_�A�����@��Ȃǐꑮ�̋@�ւŗl�X��
�@�߂z���A���Ȃ茵�������Y���܂ʌY�����Ă��邪�A���ʂ̂قǂ͔����Ȃ��̂�
�����B�펞�łȂ��Ƃ��������m�Ŗ����U�炵�Ă������A���b�̂Ȃ��b�ł���B


(�]�k3)
�@���̊O���v���Ƃ������ׂ��t�����X�E�I�[�X�g���A�����̔w�i�ɁA�g���R���őΗ�����t����
�X�ƃ��V�A�̉ۑ�������������B
�X�ƃ��V�A�̉ۑ�������������B
�@���V�A����G���U���F�[�^�͂��Ƃ��Ƃ͐e���I����������Ă������A�g���R�鍑�Ƃ̓����̓�
�V�A�̗��j�I�ۑ�ŁA�g���R�Ƃ̗F�D�W����������t�����X�Ƃ̓����́A1775�N�ȗ��̓���
���ł���C�M���X���h�����邵�A���V�A�{����ɂ͐e�p�h�Ŕ����h�̍ɑ��x�X�g�D�[�W�F�t��
�̈�h������A��ؓ�ł͍s���Ȃ���肪�R�ς������B
�V�A�̗��j�I�ۑ�ŁA�g���R�Ƃ̗F�D�W����������t�����X�Ƃ̓����́A1775�N�ȗ��̓���
���ł���C�M���X���h�����邵�A���V�A�{����ɂ͐e�p�h�Ŕ����h�̍ɑ��x�X�g�D�[�W�F�t��
�̈�h������A��ؓ�ł͍s���Ȃ���肪�R�ς������B
�@�����Ŗ��g�Ƃ��ă|���p�h�D�[���v�l���h�����ꂽ�̂��A�������u��̋M�w�l�v���A�E�h�E
�{�[�����Ƃ����l���B���A�͕\�����̓t�����X�S�����g�́u�Áv�Ƃ������ꂾ���A���g�̐Ղ�
�ڍ�����Ƃ���A�V��g���s�^���{�����o�������A�u��̋M�w�l�v�͒P�ƂňÖ�B
�ڍ�����Ƃ���A�V��g���s�^���{�����o�������A�u��̋M�w�l�v�͒P�ƂňÖ�B
 �@��̋M�w�l���A�E�h�E�{�[������
�@��̋M�w�l���A�E�h�E�{�[�������@�܂��̓G���U���F�[�^����̈��l�V�����@�[���t���ė����A�g���R���Ńt�����X�Ƃ�����Ă�
�鏗���������Ă��炤�B���V�A���u���V�A�j��̎���v���L���ŁA����ɐ����B�����Ĕ����h��
�ɑ��x�X�g�D�[�W�F�t�ƑΗ����镛�ɑ����H�����c�H�[�t�Ɏ�����A�{����̐��̓o�����X��
�����ɂ�����B�����Ă���ɂ������ɐ�������B���́u��̋M�w�l�v�́A�������āA���V�A���t��
���X�����Ɉ������ꂽ�̂ł���B�t���[�h���q��͖Ԃ͂������Ċ��������킯���E�E�E�B�V��g��
�s�^���T���N�g�E�y�e���u���N�ɓ������鍠�ɂ́A�S�Ă͌������Ă����B
�鏗���������Ă��炤�B���V�A���u���V�A�j��̎���v���L���ŁA����ɐ����B�����Ĕ����h��
�ɑ��x�X�g�D�[�W�F�t�ƑΗ����镛�ɑ����H�����c�H�[�t�Ɏ�����A�{����̐��̓o�����X��
�����ɂ�����B�����Ă���ɂ������ɐ�������B���́u��̋M�w�l�v�́A�������āA���V�A���t��
���X�����Ɉ������ꂽ�̂ł���B�t���[�h���q��͖Ԃ͂������Ċ��������킯���E�E�E�B�V��g��
�s�^���T���N�g�E�y�e���u���N�ɓ������鍠�ɂ́A�S�Ă͌������Ă����B
�@�ł��A���̗����҂ł���u��̋M�w�l�v�̐��̂�?
�u���m�j��������b�W�v�ʊق̑�3�b�ɂ��̋����̎j����������Ă���B
(TopPage�����ׂ܂����A���ڂ�URL�́ˁ@http://seiyoushi.wakatono.jp/page004.html�@)
|
