このrosanbo城の話は、1970.Hachetteの“Merveilles des chateaux de Bretagne et de
Vendee”という分厚い本から、ふと開いたページにあった“Rosanbo”の章を訳出して編集したも
のである。特にこの城が有名だとか、特別な一族の所有だとか、そのような選択理由はない。
Vendee”という分厚い本から、ふと開いたページにあった“Rosanbo”の章を訳出して編集したも
のである。特にこの城が有名だとか、特別な一族の所有だとか、そのような選択理由はない。
イル・ド・フランス地方から始まり、プロヴァンス地方、ノルマンディー地方、ラングドック、ギュ
イエンヌ地方、そしてブルゴー二ュ、フランシュ・コンテ地方とそれぞれに分厚い一冊となってい
る城館好きフランス人らしいHachetteのシリーズの中から、この「ブルターニュ、ヴァンデ地方」
を選び、たまたま捲ったページに載っていたのが、今からご紹介する“Chateau de Rosanbo”だ
ったということである。従って「ある城館」と題した次第である。
イエンヌ地方、そしてブルゴー二ュ、フランシュ・コンテ地方とそれぞれに分厚い一冊となってい
る城館好きフランス人らしいHachetteのシリーズの中から、この「ブルターニュ、ヴァンデ地方」
を選び、たまたま捲ったページに載っていたのが、今からご紹介する“Chateau de Rosanbo”だ
ったということである。従って「ある城館」と題した次第である。
フランスは、ブルターニュ地方。この地方はフランスの西端で、ヨーロッパ大陸がこの地で果
て、死者が西の海へ旅立つための最後の土地と信じられてきた。
て、死者が西の海へ旅立つための最後の土地と信じられてきた。
つまり霧深い死の国、そんな陰鬱なイメージのある地方である。
ここに紹介するロザンボ城は、そんなブルターニュ地方の北西部の海の近く、一本の川の源
近くにある古い城だ。
近くにある古い城だ。
いつからこの地に城が建てられていたか史料を追ってみても、歴史の闇の中にその起源を
見出せない、そんな古い歴史のある城である。
見出せない、そんな古い歴史のある城である。

フランスの城にも色々とあり、古代からの城砦が増築・改築を経て今に至るものから、ルネ
サンス期、あるいは18世紀頃に、にわかに建立したものもある。このロザンボの城は、前者に
属するもので、古代の民族国家とのかかわりまで語られるほどの、膨大な歴史を秘めた城だ。
サンス期、あるいは18世紀頃に、にわかに建立したものもある。このロザンボの城は、前者に
属するもので、古代の民族国家とのかかわりまで語られるほどの、膨大な歴史を秘めた城だ。
ローシュ・シュル・ル・ボーという小川が近くを流れているが、ロザンボという名の由来はこの
川にあるらしい。
川にあるらしい。



城の廊下に夜になると白衣の夫人の幽霊が出没するらしいが、その夫人が城の一族のいつ
の時代、誰の亡霊なのか、そんな調査すら、この城のもつ長大な歴史の中では結論が出ない
らしい。
の時代、誰の亡霊なのか、そんな調査すら、この城のもつ長大な歴史の中では結論が出ない
らしい。
この城、あるいは城主一族の名は、11世紀頃から史料に登場してくる。1050年にはすでに、
有力な土豪勢力として領地を拡大していたコスカエ家の所城となっている。
有力な土豪勢力として領地を拡大していたコスカエ家の所城となっている。
第一回十字軍に参加した一族の者も確認されており、遠くエーゲ海のある島にコスカエの名
を刻んだ墓標もあるそうだ。
を刻んだ墓標もあるそうだ。


十字軍 十字軍の軍船
また、第六回十字軍に参加したユオン・ド・コスカエは、従軍中に乗船が難破しそうになり、奇
跡的にも救われた体験から、神への感謝に礼拝堂を城に建造した。
跡的にも救われた体験から、神への感謝に礼拝堂を城に建造した。
フランスのいわゆる名家名門の貴族家系は、その発祥を大体、11〜12世紀に求めている。
「12世紀より続く由緒ある名門....」という具合だ。従って、このコスカエ家も、フランスに名の残る
名門貴族らと、まったくひけをとらない家格をもっていたわけだ。
「12世紀より続く由緒ある名門....」という具合だ。従って、このコスカエ家も、フランスに名の残る
名門貴族らと、まったくひけをとらない家格をもっていたわけだ。
しかし、フランスの歴史の中に、「コスカエ家」などという貴族名は、とんと現れない。
そう、よくある話だが、17世紀に至って、この家系は絶えてしまうからだ。



その間の約500年、フランスは国王権力による中央集権化が進み、地方の諸侯、中小領主
たちの独立的な存在が弱体化していった。この大きな流れの中で、いち早く、中央の国王のも
とへ家臣として仕えた貴族たちは、その後のフランス史の中に、「名門貴族」として名をとどめ
ることになる。
たちの独立的な存在が弱体化していった。この大きな流れの中で、いち早く、中央の国王のも
とへ家臣として仕えた貴族たちは、その後のフランス史の中に、「名門貴族」として名をとどめ
ることになる。
それをせず、地方の領地の中にとどまったまま、経済的にも零落していった貴族らは、血筋
だけは立派だが、「歴史」の中に埋もれた無名の存在となっていく。
だけは立派だが、「歴史」の中に埋もれた無名の存在となっていく。
ことにブルターニュ地方の貴族は在郷色が強く、頑固に領地や所城にとどまったケースが多
いので、この由緒正しきコスカエ一門も、歴史の表面に浮上することもなく、名もなき地方貴族
として、地味な歴史を積んでいったのだろう。
いので、この由緒正しきコスカエ一門も、歴史の表面に浮上することもなく、名もなき地方貴族
として、地味な歴史を積んでいったのだろう。



ロザンボ城の公式サイトにある紋章 17世紀家系図にあった紋章 城内にもイノシシの像がある
近世国家の体制の中で、にわかに台頭してくるのが、司法官や大商人といった新興勢力。と
はいえ彼らは、身分は卑しい。一代の傑物がその実力や幸運で、急に名を成したような氏素
性のあやしい連中だ。しかし、その経済的な基盤は、すさまじいものがある。
はいえ彼らは、身分は卑しい。一代の傑物がその実力や幸運で、急に名を成したような氏素
性のあやしい連中だ。しかし、その経済的な基盤は、すさまじいものがある。
そこで、彼ら新興勢力は、自分たちに不足している「肩書」というものを、なんとか金銭で補お
うとする。官職まで売買できる風潮に乗っかって、貴族の領地や肩書まで買い取ろうと躍起に
なった。17世紀になれば、百年前の一商人が「侯爵様」として肩で風を切る。
うとする。官職まで売買できる風潮に乗っかって、貴族の領地や肩書まで買い取ろうと躍起に
なった。17世紀になれば、百年前の一商人が「侯爵様」として肩で風を切る。



しかし、「血筋」というものはそうも行かない。オハナとタロベエの息子はあくまでジロベエなの
だ。そこで、彼らは、今度は、経済的に零落した名門貴族の娘たちとの婚姻を求めた。
だ。そこで、彼らは、今度は、経済的に零落した名門貴族の娘たちとの婚姻を求めた。
一方で品格もあり、由緒も歴史もある貴族たちも、崩れかけた城に荒れ果てた領地のままで
は、ご先祖様に申し訳が立たぬし、それよりまず生活が成り立たない。そこで、これら、新興勢
力たちの経済的な援助を求めて、娘を嫁入りさせたり、息子の妻に迎えたりして急場を凌ぐこ
とを望んだ。
は、ご先祖様に申し訳が立たぬし、それよりまず生活が成り立たない。そこで、これら、新興勢
力たちの経済的な援助を求めて、娘を嫁入りさせたり、息子の妻に迎えたりして急場を凌ぐこ
とを望んだ。
このロザンボの城にも、ついにそんな時代の流れが押し寄せる。
 Louis Le Peletier (1662-1730)
Louis Le Peletier (1662-1730) 1688年、ジュヌヴィエーヴ・ド・コスカエ・ド・ロザンボという花嫁が、パリ高等法院参事官ルイ・
ル・ペルティエと結婚。花嫁の父親、つまりロザンボ城主ジョゼフ・ド・コスカエ・ド・ロザン(1633-
99)がブルターニュ高等法院顧問官もやっていた関係もあったかも知れない。
ル・ペルティエと結婚。花嫁の父親、つまりロザンボ城主ジョゼフ・ド・コスカエ・ド・ロザン(1633-
99)がブルターニュ高等法院顧問官もやっていた関係もあったかも知れない。
しかも、このジュヌヴィエーヴ嬢、悲しいかな、コスカエ家の女相続人、つまり、この由緒正し
き名家の唯一の相続者なのだ。血筋をひく最後の者として、その全財産(多分、古びた城と貧
弱な領地のみ)もろとも、ル・ペルティエのもとへ嫁いだのだ。
き名家の唯一の相続者なのだ。血筋をひく最後の者として、その全財産(多分、古びた城と貧
弱な領地のみ)もろとも、ル・ペルティエのもとへ嫁いだのだ。
それでも、この婚姻によって、中央に絶大な司法権力を有する裕福なル・ペルティエ家のもと
で、コスカエ一族の血を絶やさずにつなげ、後は、時代の流れに乗った司法貴族の中に、脈々
と生き続ければよろしいわけだ。
で、コスカエ一族の血を絶やさずにつなげ、後は、時代の流れに乗った司法貴族の中に、脈々
と生き続ければよろしいわけだ。
ところがだ。哀しい話になる。
ジュヌヴィエーヴ・ド・コスカエ・ド・ロザンボは、1693年に30歳にして他界。結婚後、わずか5
年のことだ。後にパリ高等法院首席議長になるルイ・ル・ペルティエ(父親も同名なのでルイ3世
とも呼ばれる。1690-1770)を産んで、名門コスカエ家の血筋をこの子に託し、この世から去っ
てしまった。
年のことだ。後にパリ高等法院首席議長になるルイ・ル・ペルティエ(父親も同名なのでルイ3世
とも呼ばれる。1690-1770)を産んで、名門コスカエ家の血筋をこの子に託し、この世から去っ
てしまった。
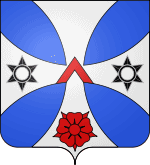

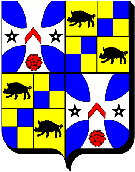
ル・ペルティエ家の紋章 コスカエ・ロザンボ家の紋章 ル・ペルティエ・ロザンボ家の紋章
さぞかし無念だったことだろう。時代の潮流とはいえ、一族のために、成り上がりの参事官と
の結婚に臨み、そして、他家の後継者を産むや、ただひとり世を去る運命は。体内に流れる名
門コスカエ数世紀の貴族の血、平民との婚姻という屈辱に忍んで保とうとしたその血流が、若く
して死ぬ我が身もさることながら、子孫の繁栄を見ずに世を去る哀しみ、それは想像に難くな
い。
の結婚に臨み、そして、他家の後継者を産むや、ただひとり世を去る運命は。体内に流れる名
門コスカエ数世紀の貴族の血、平民との婚姻という屈辱に忍んで保とうとしたその血流が、若く
して死ぬ我が身もさることながら、子孫の繁栄を見ずに世を去る哀しみ、それは想像に難くな
い。
夫、ル・ペルティエの方は、今度はパリ高等法院主席議長の娘シャルロット・アンリエット・ル・
メーラ・ド・ヴェルヴィルと再婚し、一女二男をもうける。
メーラ・ド・ヴェルヴィルと再婚し、一女二男をもうける。
ル・ペルティエからすれば、貴族の土地と名を得て、再婚によって、司法官としての地歩も固
めたわけで、一挙両得の感である。
めたわけで、一挙両得の感である。
ともかく、こうして、ロザンボ城は、諸国の城のご他聞にもれず、司法貴族の所有するところと
なった。もはや、そこには、城と共に歴史を刻んできた騎士たちとは、大いに趣を異にしている
人たちしかいない。
なった。もはや、そこには、城と共に歴史を刻んできた騎士たちとは、大いに趣を異にしている
人たちしかいない。



しかし、中央に勢力を構えている一族であれば、地方貴族の子弟が長年の軍隊勤務などで
ようやく手にすることが出来るような名誉を、いとも簡単に手に入れてしまうものだ。
ようやく手にすることが出来るような名誉を、いとも簡単に手に入れてしまうものだ。
ル・ペルティエの再婚相手の実家の力によって、このロザンボの土地に「侯爵領」の認可がも
たらされる。
たらされる。
すなわち、この地の所有者は、「ロザンボ侯爵」を名乗れることになったわけである。(ジュヌ
ヴィエ―ヴの息子ルイはロザンボ侯となっている)
ヴィエ―ヴの息子ルイはロザンボ侯となっている)
陰鬱な霧の国ブルターニュの古い城ロザンボに、新しい時代の息吹が吹き込まれた。


女相続人のジュヌヴィエ―ヴの息子ルイの娘フランソワーズ・マルティーヌなどモンモランシ
―・リュクサンブール家に嫁いでいるので、名門とは言え地方貴族コスカエの血も、ル・ペルテ
ィエ家のおかげで、とんでもない大貴族と血縁になったものである。(余談1)
―・リュクサンブール家に嫁いでいるので、名門とは言え地方貴族コスカエの血も、ル・ペルテ
ィエ家のおかげで、とんでもない大貴族と血縁になったものである。(余談1)
ル・ペルティエは、父親クロード・ル・ペルティエがあのコルベール財務長官の後任者とあっ
て、当時のフランスでも屈指の資産家だ。そこで、彼は1712年、職を引退すると、このロザンボ
城の大修復作業に着手した。
て、当時のフランスでも屈指の資産家だ。そこで、彼は1712年、職を引退すると、このロザンボ
城の大修復作業に着手した。


城が中世風の無骨な城砦的な建物部分と、近世風の貴族的居館部分とになっているのは、
この時期の建て増し工事による。
この時期の建て増し工事による。
ル・ペルティエ一族は、18世紀を通じてロザンボ城を所有していく中で、一族が手に入れた
「ロザンボ侯爵」の称号を歴史の表面に浮上させた。戦場の武勲でも国王の恩寵でもなく、司
法畑のやりくりの中で入手した肩書ではあるが、豪奢な馬車や大勢の従僕や豪華な屋敷を伴
って、その名をパリの都に知れ渡らせた。
「ロザンボ侯爵」の称号を歴史の表面に浮上させた。戦場の武勲でも国王の恩寵でもなく、司
法畑のやりくりの中で入手した肩書ではあるが、豪奢な馬車や大勢の従僕や豪華な屋敷を伴
って、その名をパリの都に知れ渡らせた。


あのサン・シモン公爵が「回想録」の中で、町人や司法官らが買い取った「価値のない」侯爵
位と散々コケにしているものではあるが、ブルターニュの田舎に埋もれていたロザンボの名
を、ここまで引き立ててくれたのは、紛れもなくル・ペルティエ家なのである。
位と散々コケにしているものではあるが、ブルターニュの田舎に埋もれていたロザンボの名
を、ここまで引き立ててくれたのは、紛れもなくル・ペルティエ家なのである。

代々ルイを名として、このル・ペルティエ家はある時は有力な司法界の家柄と、またある時
は、ヴォーバン元帥の孫娘のような軍人貴族などと婚姻を結びながら、「ル・ペルティエ・ド・ロ
ザンボ」の家名を歴史の中に刻んでいった。・・・・
は、ヴォーバン元帥の孫娘のような軍人貴族などと婚姻を結びながら、「ル・ペルティエ・ド・ロ
ザンボ」の家名を歴史の中に刻んでいった。・・・・
ところが、その栄華も一世紀とは続かない。
つまり、その名誉や称号や財産が、逆に命取りになる時代が到来するのだ。
1789年、フランス革命である。

フランス王室海軍の110門艦「ブルターニュ号」は革命政府の三色旗をつけて「革命号」となった。(1793.ブレスト港)
大革命は、容赦なくこの一族を巻き込んでいった・・・

1787年、このロザンボ城の令嬢アリーヌ・テレーズ・ル・ペルティエ・ド・ロザンボが、パリの社
交界の名士たちの祝福を受けながら、華々しく婚礼の祝典を催した。相手は、やはりブルター
ニュの貴族で近衛騎兵連隊大尉のシャトーブリアン伯爵である。
交界の名士たちの祝福を受けながら、華々しく婚礼の祝典を催した。相手は、やはりブルター
ニュの貴族で近衛騎兵連隊大尉のシャトーブリアン伯爵である。
この幸せに満ちた婚礼式典の2年後、フランス大革命が勃発するのだ。


ロザンボ城の当時の城主は、花嫁の父親でパリ高等法院判事だったルイ(ルイ5世)・ル・ペ
ルティエ・ド・ロザンボだったが、反革命容疑で革命政府によって逮捕。
ルティエ・ド・ロザンボだったが、反革命容疑で革命政府によって逮捕。
貴族身分の者は、この不幸な時代では、よほど積極的に革命政府に貢献する活動でもしな
い限り、必ず何らかの「容疑」によって身柄を拘束されてしまう。そして、逮捕されれば、まず間
違いなくギロチンで処刑である。
い限り、必ず何らかの「容疑」によって身柄を拘束されてしまう。そして、逮捕されれば、まず間
違いなくギロチンで処刑である。
その「容疑」は、本人のみならず、一族郎党すべてに及び、一家の女子供に至るまで一網打
尽にされて、裁判らしい裁判もなく、ギロチン刑が確定する「恐怖政治」の時代。
尽にされて、裁判らしい裁判もなく、ギロチン刑が確定する「恐怖政治」の時代。
そこで、ロザンボの一族も皆が逮捕され、死の控え間のような監獄へ連行されてしまう。
ルイ・ル・ペルティエの妻マルグリット(有名な法相マルゼルブの娘)や、16歳の息子や娘夫
婦、つまり1787年結婚したばかりの若夫婦であるシャトーブリアン伯爵夫妻も、容赦なく捕縛さ
れてしまった。(余談3)
婦、つまり1787年結婚したばかりの若夫婦であるシャトーブリアン伯爵夫妻も、容赦なく捕縛さ
れてしまった。(余談3)

そして、全員有罪、つまりギロチン刑だ。
国王ルイ16世の弁護人を引き受けた勇気あるマルゼルブ、つまりルイ・ル・ペルティエ・ド・ロ
ザンボの義父も相前後して、やはりギロチン刑に処せられた。
ザンボの義父も相前後して、やはりギロチン刑に処せられた。


ギロチン刑を待つ貴族たち(1794) 革命広場(現・コンコルド広場)でのギロチン刑
ここにふたつのドラマがあった。・・・

当時の革命裁判所の事務処理は、日々の大量の裁判のおかげでかなりずさんに行なわれ
ていた。同名異人を処刑してしまったり、同名の伯爵と子爵がいたら両方とも逮捕してしまった
り、ともかく酷いものだった。
ていた。同名異人を処刑してしまったり、同名の伯爵と子爵がいたら両方とも逮捕してしまった
り、ともかく酷いものだった。
そこで、判決文が読まれた際に、16歳の息子ロザンボ侯爵の死刑判決文に対して、60歳に
なる父ルイ・ル・ペルティエが身代わりに名乗りを上げたときも、裁判官はまったく気づかなか
ったのだ。
なる父ルイ・ル・ペルティエが身代わりに名乗りを上げたときも、裁判官はまったく気づかなか
ったのだ。
こうして、16歳の息子ロザンボ侯ルイは、父の身代わりのおかげで、裁判所の囚人記録簿か
ら名を抹消され、革命時代を生き延びることが出来た.....。
ら名を抹消され、革命時代を生き延びることが出来た.....。
もうひとつのドラマは、奇妙な巡り合せだった。

ルイ・ル・ペルティエの娘で1794年に処刑されたアリーヌ・テレーズの夫シャトーブリアン伯爵
は、実は、有名な作家フランソワ・ルネ・ド・シャトーブリアンの実兄。この作家にとっては、かけ
がえのない優しい兄で、その処刑は彼を深い悲しみに沈めたものだった。
は、実は、有名な作家フランソワ・ルネ・ド・シャトーブリアンの実兄。この作家にとっては、かけ
がえのない優しい兄で、その処刑は彼を深い悲しみに沈めたものだった。
シャトーブリアンの名著「墓の彼方の回想」の中にこんな話がある。
1820年、つまり兄夫婦をギロチンで殺した大革命も、終結してすでに20余年の後のことだ。あ
る人がシャトーブリアン家の名の彫られた指輪をカセット街で拾ったからと、彼のもとへ届けて
くれた。
る人がシャトーブリアン家の名の彫られた指輪をカセット街で拾ったからと、彼のもとへ届けて
くれた。
彼は二つのリングが壊れて片方にぶらさがり、かなり損傷の激しかったその指輪を見て大変
に驚いた。確かに、その指輪には、シャトーブリアン家の名が刻まれている。しかも、紛れもな
く、兄嫁の名がそこに彫られており、まさしく兄が兄嫁に送った結婚指輪そのものではないか。
に驚いた。確かに、その指輪には、シャトーブリアン家の名が刻まれている。しかも、紛れもな
く、兄嫁の名がそこに彫られており、まさしく兄が兄嫁に送った結婚指輪そのものではないか。

愛する兄と若い花嫁がギロチン台に上った1794年4月22日、死刑囚護送車の中の彼女の指
からこぼれ落ちたものなのか? または、処刑された後に指から抜け落ちたものなのか?
からこぼれ落ちたものなのか? または、処刑された後に指から抜け落ちたものなのか?
いずれにしても、20年以上の歳月の後に、ふと彼のもとへ戻ってきた悲運な兄嫁の結婚指輪
を前に、彼は愕然としてしまったらしい。この奇妙な巡り合せには、なにか人智を超越した、激
しい人間の情念の作用のようなものを感じさせる。
を前に、彼は愕然としてしまったらしい。この奇妙な巡り合せには、なにか人智を超越した、激
しい人間の情念の作用のようなものを感じさせる。


Henriette Genevieve d'Andlau comte de Tocqueville
ともかく、ロザンボ城の一族がこうして革命の名の下にギロチン台の露と消えてしまい、ルイ・
ル・ペルティエ氏の咄嗟の判断で、奇跡的にも一命を取り留めた息子ロザンボ侯爵ルイ(6世)
が、唯一の相続人となる。
ル・ペルティエ氏の咄嗟の判断で、奇跡的にも一命を取り留めた息子ロザンボ侯爵ルイ(6世)
が、唯一の相続人となる。
そしてアンリエット・ジュヌヴィエーヴ・ダンドロー(あのポリニャック夫人の父親ポラストロン伯
爵の姉マリー・アンリエット・ド・ポラストロンの孫娘)というヴィジェ・ルブランがその美しい肖像
画を残しているような奥方を娶り、80歳近くまで生き、第二次王政復古の1815年、ルイ18世の
もと貴族院議員になる等、革命後にその身分の復権を果たしてゆくのである。(もう一人の姉ル
イーズ・マドレーヌはノルマンディー地方の貴族トクヴィル伯爵に嫁いでおり、有名な政治思想
家で外務大臣にもなるトクヴィルの母となる)(余談4)
爵の姉マリー・アンリエット・ド・ポラストロンの孫娘)というヴィジェ・ルブランがその美しい肖像
画を残しているような奥方を娶り、80歳近くまで生き、第二次王政復古の1815年、ルイ18世の
もと貴族院議員になる等、革命後にその身分の復権を果たしてゆくのである。(もう一人の姉ル
イーズ・マドレーヌはノルマンディー地方の貴族トクヴィル伯爵に嫁いでおり、有名な政治思想
家で外務大臣にもなるトクヴィルの母となる)(余談4)


comte de Mac-Mahon Patrice de Mac-Mahon
また復権したロザンボ侯ルイ6世だが、その娘のマリー・アンリエットが17世紀にアイルランド
からフランスに帰化した軍人貴族の一族マク・マオン伯爵の息子シャルル・マリーに嫁ぐのであ
るが、その弟パトリスは1873年に第3代フランス大統領となる人物だ。
からフランスに帰化した軍人貴族の一族マク・マオン伯爵の息子シャルル・マリーに嫁ぐのであ
るが、その弟パトリスは1873年に第3代フランス大統領となる人物だ。

ひとつの城館には、それなりの歴史があり、そして歴史には人々の命の足跡が刻まれる。
どんな人で、どんな人生を送っていったか.....。城の苔むした壁石や磨耗した敷石は、それを
知っている。
知っている。
しかし我々は、想像するだけである。
だが、確実に言えることは、そこに生きた人々がどんな人々であれ、皆、精一杯に自分の人
生の主役を演じていたということだ。
生の主役を演じていたということだ。
分厚い書物を気ままに開き、そこに載っていたこのロザンボ城にすら、これだけの歴史とドラ
マがあるのだから・・・・
マがあるのだから・・・・

余談コーナー
(余談1)
1741年結婚の下記2人のこと。
Francoise Martine Le Peletier de Rosanbo (1722-1750)
Joseph Maurice Annibal de Montmorency-Luxembourg (1717-62)
(余談2)
この肖像画は娘の一人であり画才のあったスザンヌ・ギヨメット・ル・ペルティエ・ド・ロザンボ
Suzanne Guillemette Le Peletier de Rosanbo (1773-1800),が描いたものである。
Suzanne Guillemette Le Peletier de Rosanbo (1773-1800),が描いたものである。
スザンヌは良家の子女として音楽・舞踏・作法・刺繍等の教育をしっかりと受ける中でも素描
と絵画の習得に熱心で、幾点かの作品が残されている。この父親の横顔もそのひとつで、彼
女は基礎をマスターすると身の周りの人の肖像を好んで描いていた。
と絵画の習得に熱心で、幾点かの作品が残されている。この父親の横顔もそのひとつで、彼
女は基礎をマスターすると身の周りの人の肖像を好んで描いていた。
また、当時の王立特待生学校の授業で行っていた有名画家たちの版画の模写を描くことに
よるトレーニングと同じ指導のもと、下の作品のようなものも残っている。これはグルーズの
1755年アカデミー出品作「聖書の朗読」の版画の模写で彼女が20歳の1792年の作品である。
よるトレーニングと同じ指導のもと、下の作品のようなものも残っている。これはグルーズの
1755年アカデミー出品作「聖書の朗読」の版画の模写で彼女が20歳の1792年の作品である。
スザンヌ・ギヨメットは1792年同じ歳の従兄弟ドーネイ伯爵シャルル・ルイ・マリーCharles-
Louis-Marie Le Pelletier d'Aunayと結婚したが、27歳で1800年に亡くなっている。両親と姉を94
年ギロチンで同時に失った衝撃は相当なものだったろう。革命の混乱がようやく終息した頃に
亡くなっているのはなんとも哀しい。
Louis-Marie Le Pelletier d'Aunayと結婚したが、27歳で1800年に亡くなっている。両親と姉を94
年ギロチンで同時に失った衝撃は相当なものだったろう。革命の混乱がようやく終息した頃に
亡くなっているのはなんとも哀しい。
ル・ペルティエ・ド・ロザンボ家には、4女1男がいたが、彼女は三女だった。1771年に長女の
アリーヌ、翌年にルイーズ、その翌年にスザンヌが年子で生まれている。(四女アントワネットは
夭折)唯一の男子のルイは、スザンヌの4つ下で生まれている。
アリーヌ、翌年にルイーズ、その翌年にスザンヌが年子で生まれている。(四女アントワネットは
夭折)唯一の男子のルイは、スザンヌの4つ下で生まれている。
トクヴィル伯爵に嫁いでいる次女ルイーズと混同されてルイーズ・マドレーヌ・スザンヌ・ギヨメ
ット(1773-1805)となっている資料もあるが、それは誤りであろう。姉妹が1本化されては困る。
ット(1773-1805)となっている資料もあるが、それは誤りであろう。姉妹が1本化されては困る。

(余談3)
シャトーブリアン伯爵(正確にはコンブール伯爵Comte de Combourg,Jean Baptiste Auguste
de Chateaubriand)は、亡命貴族軍(亡命した貴族により組織された反革命軍。対フランス革命
軍のオーストリア、ドイツ等の同盟軍に合流していた)に参加すべく後に作家・政治家として有
名になる弟フランソワ・ルネと1792年7月15日パリを出発した。兄の伯爵はブリュッセルで、妻
のアリーヌ・テレーズの母方の伯母でマルゼルブ法相の娘フランソワーズ・ポーリーヌの夫モン
ボワシエ侯爵(Charles Philipppe Simon de Monboissier Beaufort-Canillac)が率いる貴族軍に
入り、侯爵の副官となった。
de Chateaubriand)は、亡命貴族軍(亡命した貴族により組織された反革命軍。対フランス革命
軍のオーストリア、ドイツ等の同盟軍に合流していた)に参加すべく後に作家・政治家として有
名になる弟フランソワ・ルネと1792年7月15日パリを出発した。兄の伯爵はブリュッセルで、妻
のアリーヌ・テレーズの母方の伯母でマルゼルブ法相の娘フランソワーズ・ポーリーヌの夫モン
ボワシエ侯爵(Charles Philipppe Simon de Monboissier Beaufort-Canillac)が率いる貴族軍に
入り、侯爵の副官となった。
弟はそのままトリエルまで行き、王弟たちやカストル元帥らが指揮してライン・モーゼル両河
畔に展開している亡命貴族軍の最前線に入った。
畔に展開している亡命貴族軍の最前線に入った。
 Francoise Pauline de Lamoignon(1753-1827)
Francoise Pauline de Lamoignon(1753-1827) その後、兄弟はブリュッセルで再会するが、兄の伯爵は、亡命貴族の財産没収の法令が発
布されたのを受けて帰国するところだった。長男だから資産の保持に動くのは仕方ないが、亡
命貴族が帰国の場合は死刑だとの革命政府の宣告を知らなかったのか、彼は弟に当座の資
金を手渡すと、帰国の途に。そして、こうして逮捕、一家もろともギロチンに送られてしまったの
である。もちろん、一番革命政府から危険視されていたのはマルゼルブだったので、一族の逮
捕は伯爵の責任とは言えない。また直接的には、義父のル・ペルティエが反革命文書の隠匿
という容疑で逮捕されたのが始まりだった。つまり貴族の逮捕・処刑には理由などないのだ。
布されたのを受けて帰国するところだった。長男だから資産の保持に動くのは仕方ないが、亡
命貴族が帰国の場合は死刑だとの革命政府の宣告を知らなかったのか、彼は弟に当座の資
金を手渡すと、帰国の途に。そして、こうして逮捕、一家もろともギロチンに送られてしまったの
である。もちろん、一番革命政府から危険視されていたのはマルゼルブだったので、一族の逮
捕は伯爵の責任とは言えない。また直接的には、義父のル・ペルティエが反革命文書の隠匿
という容疑で逮捕されたのが始まりだった。つまり貴族の逮捕・処刑には理由などないのだ。


Guillaume-Chretien de Lamoignon de Malesherbes(左)
姉のセノザン侯夫人(Marquis de Rosny et de Senozan,Anne-Nicole de Lamoignon de Malesherbes・右)も、もう一
人の76歳になる姉バルブ・ニコールや孫娘タレイラン・ペリゴール夫人(30歳)と共に処刑されている。
人の76歳になる姉バルブ・ニコールや孫娘タレイラン・ペリゴール夫人(30歳)と共に処刑されている。
マルゼルブは、革命前の旧体制下で、様々な官職に就いたが、特に出版統制局長官の時
代、啓蒙思想の出版物の発行を統制するどころか擁護し、王室と教会とは犬猿だった。官憲
の手が及ばぬよう執筆者に「外国での出版の体裁をとるよう」などと裏技まで示唆しているほど
熱心だった。啓蒙思想が平等思想に立脚するものであり、その伝搬が大革命の誘因となった
わけであるが、かつての敵とも言える国王ルイ16世の逮捕が不当であると見ると、彼は命の危
険も顧みずに国王の弁護人を名乗り出た。彼は単に正義の味方・不正の敵たらんと行動し、
相手が強大な権力であっても怯むことはしない男だった。
代、啓蒙思想の出版物の発行を統制するどころか擁護し、王室と教会とは犬猿だった。官憲
の手が及ばぬよう執筆者に「外国での出版の体裁をとるよう」などと裏技まで示唆しているほど
熱心だった。啓蒙思想が平等思想に立脚するものであり、その伝搬が大革命の誘因となった
わけであるが、かつての敵とも言える国王ルイ16世の逮捕が不当であると見ると、彼は命の危
険も顧みずに国王の弁護人を名乗り出た。彼は単に正義の味方・不正の敵たらんと行動し、
相手が強大な権力であっても怯むことはしない男だった。
有徳の士で思想家のみならず国民からも人気の人物で、革命政府による逮捕に際してはマ
ルゼルブ村の議会は彼の無罪を主張し、その公民精神と市民への援助、良き共和国の人民
であることを証言したくらい。しかし革命政府は取り合わなかった・・・
ルゼルブ村の議会は彼の無罪を主張し、その公民精神と市民への援助、良き共和国の人民
であることを証言したくらい。しかし革命政府は取り合わなかった・・・
処刑の日、彼は刑場に引き立てられて行くときにつまずいてしまう。
「縁起が悪いな。ローマ人ならば行くのをやめるだろうが、そうも行かないか」
と最後まで冗句を飛ばしていたという。
(余談4)
政治思想家トクヴィルとは、言うまでもなくアレクシ・アンリ・シャルル・クレレル・ド・トクヴィル
Alexis-Henri-Charles Clerel de Tocqueville (1805-1859)のことである。ノルマンディーの古い貴
族家系だが、議員、裁判官、外務大臣等を歴任し、引退後は著述家となったフランスが誇る思
想家、歴史家だ。
Alexis-Henri-Charles Clerel de Tocqueville (1805-1859)のことである。ノルマンディーの古い貴
族家系だが、議員、裁判官、外務大臣等を歴任し、引退後は著述家となったフランスが誇る思
想家、歴史家だ。
ル・ペルティエ・ド・ロザンボ家の次女ルイーズがトクヴィル伯爵と結婚。男ばかり3人を産んだ
が、その末っ子がアレクシである。
が、その末っ子がアレクシである。
ギロチンを辛くも逃れた父の伯爵は一晩で髪が白髪化してしまったという体験を語り、両親・
姉を同時にギロチンで失った母であるルイーズはあの体験で精神を病み、遠い古き良き時代
の回想の中に生きていたという。そんな家庭環境の中で、トクヴィルはリベラル思想の研究に
情熱を注ぎ、アメリカに渡り当地のデモクラシーの実地の見聞を深めていくのである。
姉を同時にギロチンで失った母であるルイーズはあの体験で精神を病み、遠い古き良き時代
の回想の中に生きていたという。そんな家庭環境の中で、トクヴィルはリベラル思想の研究に
情熱を注ぎ、アメリカに渡り当地のデモクラシーの実地の見聞を深めていくのである。



アレクシと父トクヴィル伯爵 母ルイーズ・ル・ペルティエ 政治思想家トクヴィル
|
